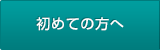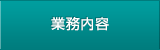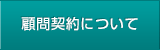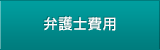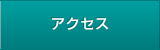最近のエントリー
カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 里村文香
- 桑原 亮
- 詐欺問題
- 交通事故 (4)
- 労働問題
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)
月別 アーカイブ
- 2022年6月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (5)
- 2021年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (10)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (11)
- 2019年6月 (11)
- 2019年5月 (11)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (25)
- 2019年2月 (20)
- 2019年1月 (24)
- 2018年12月 (25)
- 2018年11月 (18)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (3)
- 2016年8月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (6)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2011年2月 (9)
- 2011年1月 (21)
- 2010年12月 (25)
- 2009年9月 (1)
HOME > 旧コラム > 企業法務 > 中小企業の株式対策エッセンス【企業法務】
旧コラム
現在のコラムはこちらから
< 不動産を利用した節税スキームの法的リスク【不動産問題】 | 一覧へ戻る | 破産免責の徹底解説【借金問題】 >
中小企業の株式対策エッセンス【企業法務】
今回は、中小企業の株式対策として、株式の分散、株式の集中、株価対策、議決権の集中、自己資本比率など、中小企業に必須な株式対策のエッセンスを解説します。個々の問題の詳しい解説は改めてさせていただきます。
目次
株式の分散株式の集中
株価
議決権の集中
自己資本比率
まとめ
株式の分散
1.株式の分散とは
オーナーが自社株式の100%を保有しておらず、他の親族、役員、従業員、共同経営者らも株式を保有している状態を、株式の分散と呼びます。過去には、株式会社の設立時の発起人が7名必要だった時代がありました。また、中小企業でも従業員に株式を持たせることが奨励された時代もありました。
また、民法の原則は分割相続です。オーナーが100%保有していたとしても、相続により各相続人に分割承継されることがあります。
そのため、株式が分散している会社は少なくありません。
2.株式の分散の弊害
株式の分散は、上場あるいは株式公開をしていない中小企業にとって、特別にそれを必要とする事情がない限り、百害あって一利なしです。
特別なケースとは、外部資本からベンチャー投資などを受け入れるなど、どうしても経営者以外が株式を保有する必要がある場合ですね。
この点は見解が統一されつつあります。株式の分散は、株主総会等のコストが増える、経営のスピードを阻害する、M&Aや事業承継の障害になるなど、経営の足かせになるからです。
株式の分散は、中小企業の強みである機動力・スピードに反するのですね。
そもそも、会社の所有者は株主です。オーナー企業であればその実態に合わせてオーナーが100%保有するべきでしょう。
株式の集中
1.株式の集中
上述のように、株式の分散はよくないということで見解が一致しつつあります。株式が分散している会社は、現オーナーあるいは後継者に株式を集めます。これを、株式の集中あるいは集約といいます。
最近は、株式の集中に関する提案が、金融機関やコンサルタント会社から事業承継対策としてなされることが当たり前になってきました。ただし、株式の集中は法律問題です。弁護士にきちんと相談してから進めてください。
2.株式集中の方法
株式の買取りが一番穏当な手段です。なお、他人名義の株式が名義株であるときは、別途名義株の解消をします。
株式を強制的に集約する法制度も整備されつつあるところです。
事業承継問題への対策の一つとも位置付けられますでしょうか。
強制的な集約手段として特別支配株主の株式買取請求制度ができました。
以前からあった株式併合の手段を活用した少数株主排除の手段もとりやすくなっております。
株価
1.株式の集中と株価
株式の集約をするにあたって一番困るのは株価が高いケースです。株価が高いケースとしては、長年、適切な役員報酬をとらず会社に利益をプールした結果であることが多いですね。株価が高いと、株式の集約にかかるコストが跳ね上がります。税務上問題のない形での売買、株式買取請求、株式併合等のコストは株価次第ですからね。
2.株価の引下げ
M&Aで株式を売却する場面は別として、株価が高いことには何らのメリットもありません。むしろ弊害が多いといえます。事業承継が絡むケースであれば、役員退職金が即効性のある株価引き下げ策として利用できます。
ただ、経営権が移譲できないケースでは使えません。
ある程度の所得税を払っても中長期的な報酬戦略をとって、会社から個人(オーナーあるいは後継者)への資産移転を進めなければなりません。
議決権の集中
1.議決権の集中
株価が高すぎるケースなど、どうしても株式の集中ができない事情があることもあります。その場合には、次善の策として、議決権の集中を図ります。
オーナーあるいは後継者の保有する株式に議決権を集めるのです。
株式の集中ができなくとも、議決権を集中することで、経営のスピード・機動力の確保、円滑な事業承継には耐えられます。
2.議決権の集中の例
議決権の集中は、種類株式あるいは属人株式を活用します。種類株式の活用とは文字どおり種類の違う株式を発行することです。
経営者以外の株主の株式を議決権なし優先配当の種類株式とするケースがイメージされやすいでしょうか。
属人株式は株主によって株式の取扱いを変えることです。{C}{C}{C}代表取締役の保有する株式の議決権を100倍にすると株主総会の開催も決議も簡単になりまね。
勿論、種類株式、属人株式の導入は高いハードルがあり、かつ法的なリスクも伴います。弁護士に相談の上で進めてください。
自己資本比率
1.自己資本比率とは
法律論とは少し離れます。自己資本比率は、自己資本/総資産(%)で表されます。
自己資本比率が高いほど、自己資金が豊富ということなので、経営の安全性が高いといわれます。
自己資本比率は、ひと昔前の銀行の与信審査では大きなウェイトを占めました。
株価が高いということは、基本的に利益を内部留保し自己資本比率も高くなるということになります。
2.自己資本比率は高いほどいいのか
大企業は別として、少なくとも中小企業に限っては、自己資本比率が高ければ高いほどいいとはいえません。もちろん、自己資本比率が低すぎると危険ですよ!営業活動をすれば、資産(売掛金等)あるいは負債(買掛金等)が膨れ、自己資本/総資産で表される自己資本比率は低くなります。
また、会社の信用を生かして銀行から借り入れて商売の幅を拡げる、あるいは資金の回転を多くして利益を増やそうとすると、当然に自己資本比率が低くなります。
中小企業は、銀行からお金を借りて(間接金融により)調達した資金を運用して、利益を拡大させるものです。すなわち、儲けようとすれば自己資本比率は下がるはずです。自己資本比率が過度に高い中小企業には成長性がありませんし、経営効率が悪いことになります。
まとめ
1.今回お話したこと
株式の分散は望ましい状態ではありませんでした。株式の集中を図る必要があり、そのための法制度も整備されつつありました。高すぎる株価の弊害は多くありました。株式の集中の障害にもなります。即効性のある役員退職金や継続的な報酬戦略が求められました。株式の集中が困難な場合には議決権の集中を考えることができます。なお、自己資本比率は高いほどいいわけではありませんでした。株主は会社の所有者です。したがって、株式対策は経営の基本となります。
株式対策を決して先送りにしないでください。
2.企業法務に詳しい弁護士に相談を
株式の集約などの株式対策は、すぐれて法律問題です。法的なリスクを伴い場面が多いですし、スキーム作りには税法の問題意識も必要とします。必ず、企業法務に精通した弁護士にご相談の上で進めてください。弁護士仲田は、企業法務に精通しているのは勿論、税法の専門知識も併せ持っております。M&Aや事業承継案件での株式対策サポートの経験も豊富です。ぜひご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院法務研究科客員准教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
広島市消費生活紛争調停委員会委員
経営革新等支援機関(中小企業庁)
M&A支援機関(中小企業庁)
カテゴリ:
(なかた法律事務所) 2022年1月19日 15:03
< 不動産を利用した節税スキームの法的リスク【不動産問題】 | 一覧へ戻る | 破産免責の徹底解説【借金問題】 >
同じカテゴリの記事
法人の自己破産に取締役全員の同意が必要なのか?
今回は、法人が自己破産を申し立てる際にどのような意思決定が必要なのかというお話をさせていただきます。
個人の自己破産は関係のない、法人の自己破産特有の問題です。
目次
Ⅰ自己破産と準自己破産との違いⅡ法人の自己破産には取締役全員の同意が必要か?
Ⅲ法人の意思決定の方法とは
Ⅳ意思決定の具体例
Ⅴ意思決定にあたっての注意点
Ⅵまとめ
Ⅰ 自己破産と準自己破産の違い
1.自己破産と準自己破産
破産法18条1項では破産手続開始申立権を「債務者」に認めています。「債務者」の申立てによって開始される破産手続を自己破産と呼びます。現在、ほとんどの破産手続が自己破産となっています。
これに対して、法人破産では、破産法19条が、理事、取締役および業務を執行する社員など役員がその地位に基づいて法人の破産手続開始申立てをすることも認めます。これら役員の申立てによる破産手続を準自己破産を呼びます。
2.自己破産と準自己破産の違い
① 破産手続開始原因の疎明責任の有無準自己破産の場合(破産法19条に基づいて役員が申立てをするとき)は、役員全員が申立人となる場合を除き、破産手続開始原因事実が存在することの疎明を要求されます(破産法19条3項)。役員の一部による申立てでは、内紛を原因として破産手続が濫用されるおそれがあるからです。
破産手続開始原因とは、支払不能または債務超過です(破産法16条1項)。支払不能とは、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態です(破産法2条11号)。債務超過は、債務につきその財産をもって完済することができない状態です(破産法16条1項括弧書)。
② 予納金額の多寡と負担
準自己破産の場合には、自己破産と比べて、裁判所に要求される予納金が額が高額になる可能性があります。かつ、準自己破産では、原則として、申し立てる役員が予納金を負担します。
③ 弁護士費用
準自己破産の場合には、原則として、会社財産から弁護士費用等を支出することはできません。
申し立てる役員が負担する必要があります。
Ⅱ 法人の自己破産には取締役全員の同意が必要か?
1.自己破産ができる「債務者」とは
自己破産ができる「債務者」(破産法18条1項)には、自然人だけではなく、法人も含まれます。法人組織として法的に要求される手続を経て有効な意思決定がなされ、同決定に基づき代表機関が申し立てた破産手続は、すべて自己破産になります。かつては、法人が「債務者」として自己破産を申立てられるのは、役員全員が申し立てるか、代表者が役員全員の同意を得て申し立てる場合に限られるという見解が一般的だったようです。一部の役員による申立ての場合にのみ破産開始原因の疎明義務が課されている(さきほどの破産法19条3項)という理由のようです。今でも、コンメンタール等では両論が併記され、役員全員の同意が必要と解説するインターネット記事も存在します。
法律が要求する機関決定に従った申立てであれば、法人の意思に基づく自己破産申立てだと考える方が自然ですね。自己破産をするために、わざわざ反対する取締役を解任して全員一致の形を作らなければならないと考えるのはとても迂遠ですし、非現実的ですよね。現在は、機関決定があればよいとする考えが一般的だと思います。少なくとも、広島地方裁判所本庁ではこの考え方で通用しております。
2.取締役全員の同意が必要なのか
法人が自己破産をするためには、取締役全員の同意を取り付ける必要はありません。裁判所は、法人の自己破産申立てにかかる添付書類として、取締役会議事録とともに、取締役全員の同意書面も指定していると思います。
一見、取締役全員の同意を取り付けなければ準自己破産になるとも思えますね。
しかし、法的に要求される手続を経て有効に意思決定がなされていれば自己破産でした。
裁判所には、機関決定(取締役会決議など)を証する書面(取締役会議事録など)を提出すれば足り、全員一致である必要はありません。
では、法的に要求される機関決定とはどのようなものなのでしょうか。次に見ていきます。
Ⅲ 法人の意思決定の方法とは
1.株式会社の場合
取締役会設置会社で業務の決定を行うのは、あくまでも取締役会です(会社法362条2項1号)。取締役でも株主総会でもありません。取締役会決議は、定款で条件を加重していない限り、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います(会社法369条1項)。
取締役会議事録を作成します。
これに対し、非取締役会設置会社では、業務の決定を行うのは、取締役です。
取締役が1人の場合には、単独で業務の決定をします(会社法348条1項)。取締役が2人以上いるときは、定款で別の定めをしない限り、取締役の過半数をもって業務を決定します(会社法348条2項)。
取締役決定書あるいは同意書を作成します。
ただし、非取締役会設置会社では、株主総会も業務の決定をする包括的権限を有します(会社法295条1項)。取締役はその決定に従わなければなりません。
株主総会決議で意思決定をする場合には、株主総会議事録を作成します。
2.有限会社その他の法人
その他の法人も株式会社と同じです。法律で要求される機関決定で足ります。特例有限会社は、基本的に非取締役会設置会社と同じと考えてください。取締役単独あるいは取締役の過半数、および株主総会です。
その他の法人も、理事会決議等、法的に要求される手続による機関決定を経ていればかまいません。理事会議事録などを作成します。
Ⅳ 意思決定の具体例
1.取締役会設置会社のケース
代表者が95パーセントの株式を保有する取締役会設置会社です。取締役は3人ですが、名前だけ借りていて疎遠な取締役が1名いる例を想定しましょう。取締役会設置会社では、業務の決定を行うのは、取締役会でしたね。反対する取締役がいても決議さえ成立すればいいです。上記会社では、取締役会を開催して破産手続開始申立てを決議します。裁判所には取締役会議事録を提出すればいいです。
2.非取締役会設置会社のケース
代表者が100パーセントの株式を保有している非取締役会設置会社です。取締役は5人ですが、同意を得られない取締役が1名いる例を想定します。非取締役会設置会社かつ取締役が2人以上の会社は、取締役の過半数をもって業務の決定しました。これに従えば、裁判所には、過半数の取締役による取締役決定書、あるいは過半数の取締役の同意書を提出することになるでしょう。
ただし、非取締役会設置会社では、株主総会も業務の決定をする包括的権限を有しました。このケースでは、代表者1人で容易に全員出席株主総会が開催できますね。臨時株主総会にて破産手続開始の申立てを決議した方が簡便です。裁判所には、臨時株主総会議事録を提出します。
Ⅴ 意思決定にあたっての注意点
1.意思決定の手続を踏む
意思決定をする際には、法定の手続をきちんと踏むことを意識してください。取締役会議事録等の機関決定を証する書面は裁判所に提出する書類であり、債権者等が閲覧することができます。また、破産に反対する役員がいれば、法定手続を経ていないとトラブルになるかもしれません。
法定手続を遵守している会社は少ないでしょう。しかし、自己破産の決定に際しては、招集通知などの手続をきちんと踏む方がよろしいでしょう。
2.意思決定の記録を残す
上述のように、法人の意思に基づく申立てであること(自己破産の申立てであること)を証する書面を裁判所に提出しなければなりません。議事録や同意書を裁判所に提出できるよう、あらかじめ弁護士等に準備をしてもらい、確実に作成してください。後で作成すればいいと放っておくと、営業停止などによる混乱が生じた結果、後から作成できないという事態も生じることがあります。
Ⅵ まとめ
1.法人自己破産には取締役全員の同意が要求されない
法人が自己破産するために、取締役などの役員全員の同意は要求されません。法人組織として法的に要求される手続を経た有効な意思決定に基づき、代表機関が自己破産を申し立てればいいだけです。法的に有効な意思決定があるのであれば、法人の意思による自己破産であり、役員がその資格で申し立てる準自己破産ではありません。
2.法人自己破産の意思決定方法
株式会社の場合、取締役会設置会社では取締役会で、非取締役会設置会社では取締役(1人の場合)、取締役の過半数(2人以上の場合)あるいは株主総会で、自己破産申立てを決定しました。その他の法人も、法定された機関決定を経れば自己破産と認められます。法人の意思決定を証する議事録等は裁判所に提出しなけばなりません。機関決定にあたっては、法的手続をきちんと踏む、きちんと記録を残すことを心がけてください。
終わりに
今回は、法人の自己破産申立てにあたって取締役など役員全員の同意が要求されるかどうかについて説明をしました。法人破産は、事前準備と段取りでその成否が決まります。法人破産に詳しい弁護士に早めにご相談ください。なかた法律事務所は、法人破産について豊富な知識、経験を有します。
この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)
◆経歴
1996年4月~ あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~ 東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~ 広島大学大学院法務研究科
2008年12月 弁護士登録
2017年~各前期 広島大学大学院客員准教授(税法担当)
◆資格等
弁護士、公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)
(なかた法律事務所) 2022年6月10日 09:26
競業があったときの競業避止義務、秘密保持義務、不正競争防止法の徹底解説【企業法務】
今回は、競業避止義務、秘密保持義務・不正競争のお話です。
退職した従業員や退任した役員が競業行為をしている、会社の技術ノウハウを盗まれた、他の従業員が引き抜かれたなどの相談は珍しくありません。同業者間での転職や、同業者による引き抜きは効率的なために必然的に多くなります。独立する際も培ってきた知識・ノウハウ・人脈を利用するのが当然でしょう。一方、企業にとって、技術・ノウハウ・顧客情報・人材の流出は死活問題です。納得できませんね。こうした理由で、競業避止義務、秘密保持義得・不正競争が絡む紛争は多々発生しています。
これまで、一般的な企業では、就業規則において副業禁止規定が設け、従業員の副業を禁止していました。
ところが、最近は、副業を認める企業が増えてきており、国をそれを後押ししています。
副業が増えれば、在職中の競業行為の可能性も増えますね。今後、競業避止義務違反・秘密保持義務違反、不正競争防止法違反の紛争が増加していくかもしれません。
目次
競業避止義務とは従業員の競業避止義務
競業避止義務違反の判断
取締役の競業避止義務
競業行為に対する措置
従業員の引き抜き行為
秘密保持義務
不正競争防止法
まとめ
Ⅰ競業避止義務とは
1.競合避止義務とは
競業避止義務は競業行為を避止する義務です。競業行為とは、取締役に関する会社法の定めでは、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をすることを意味します。ただし、実際に就業規則や合意などで定められている競業行為はそれよりも広い意味です。競業会社への就職も含まれたりします。
従業員の競業避止義務と、取締役等役員の競業避止義務とは、その根拠を異にするため、分けて考えなければいけません(考え方は重なりますが)。
競業避止義務というと、ほかに営業譲渡人の競業の禁止(商法16)が思い浮かぶでしょうか。営業譲渡をした譲渡人は、同一の市町村で同一の営業を20年間行ってはいけないとう法定の義務です。事業譲渡、株式譲渡などM&Aの契約書では、ほぼ例外なしに、競業避止義務条項が設けられています。
一定の従業員や役員は企業独自のノウハウ、秘密の技術、集約された顧客情報など企業の様々な無形の資産に接することができます。一人前の仕事をしてもらうにはそれらを積極的に教えなければいけません。従業員や役員が、ライバル企業に転職したり、事業を立ち上げて競争相手になるのは、企業からしたらフェアな行為だと思えません。私も経営者ですから、そのような心理は理解できます。競業避止義務は、企業として当然の要請といっていいでしょう。
一方で、転職の自由、営業の自由は憲法上保障される価値です。それらを制限する面がある競業避止義務には制約が存在します。
2.憲法との関係
憲法は、職業選択の自由(憲法22Ⅰ)を明文で定めます。身分な性別によって職業が固定されていた歴史を踏まえた規定です。また、同条、および財産権を保障する憲法29条は、営業の自由を保障すると解釈されています。憲法上、職業を選択するのも、事業を始めて営業するのも、本来自由です。競業行為を禁止する競業避止義務は、個人の職業選択の自由あるいは営業の自由という憲法上の権利を制限する面があることになります。
憲法は私人間の法律関係に直接適用されるわけではありません。近代憲法は、国家に対して個人の自由を保障することを本来の役割とします。しかし、競業避止義務の有効性や具体的行為が同義務に違反するかどうかの判断においては、憲法上の人権保障の趣旨が及ばされます。会社の利益、従業員・取締役の不利益および社会的利害に立って、制限期間、場所的職種的範囲、代償の有無を検討し、合理的範囲かどうかが判断され、職業選択の自由等を過度に制限し合理性がない競業避止義務の定めや合意は、公序良俗(民法90)に反して無効となります。
Ⅱ 従業員の競業避止義務
1.在職中の競業避止義務
従業員の在職中の競業避止義務は、取締役等役員のそれと違い、法律の明文で定められてはいません。しかし、在職中の従業員は、労働契約に付随する義務として、当然に、競業避止義務を負います。
労働契約はその人的・継続的な性格から当事者間の信頼関係が要請されます。労働契約法でも信義誠実の原則が特に規定されている所以です(労働契約法3Ⅳ)。労働契約の当事者双方は、信義誠実の要請に基づいて、各種付随的義務を負います。使用者の付随義務としては、安全配慮義務が代表的ですね。一方、労働者の付随義務としては、営業秘密保持義務、競業避止義務、使用者の名誉・信用を毀損しない義務などが挙げられています。
当然認められる義務ですが、就業規則や誓約書等の合意によって競合避止条項が定められいることが多いと思います。法律上当然に認められる義務であっても、その内容を具体的・詳細に定めていくことはいいことです。
なお、就業規則に競業避止義務条項を設け、さらに誓約書等の個別合意にて競業避止義務特約を締結するケースでは、両者の内容が抵触しないように注意します。特約の内容が就業規則の基準に達しない条件として無効になりかねません(労働契約法12)。就業規則の競業避止義務条項において、個別の特約を許容する旨を記載すべきと言われています。
2.退職後の競業避止義務
競業避止義務違反が問われるトラブルのうちの多くは、退職後に競業行為がなされたケースです。職業選択の自由あるいは営業の自由の観点から、従業員が退職後に競業行為をすることは原則自由です。
退職前の競業避止義務とは異なり、退職後の競業避止義務は原則として存在しません。
退職後の競業避止義務を課すためには、
① 就業規則の規定で定めておく
あるいは
② 従業員との間で個別の合意(雇用契約、誓約書等)をしておく
の方法をとっておかなければなりません。
就業規則の定め、あるいは競業避止義務の特約が存在するだけではいけません。
競業避止義務は、職業選択の自由、営業の自由という憲法上の価値との関係で、合理的な制限でなければ許容されず、無効となります。就業規則あるいは誓約書等の合意文書は、後に有効性が否定されない形で作成しなければいけません。
なお、前述のとおり、就業規則の定めと個別の合意の双方を用意する場合には、双方の内容が抵触しないよう注意してください。
Ⅲ 競業避止義務違反の判断
1.在職中の競業行為
在職中は、定めや合意のあるなしにかかわらず、競業避止義務が認められました。競業避止義務違反かどうかの判断においては、従業員の引き抜き、顧客奪取、企業秘密の漏洩等、使用者の事業活動に影響を及ぼす行為が行われているかが重視されていると言われています。企業側を保護する要請が高いため、高い役職の従業員や機密情報に密に接していた従業員の行為は競業避止義務違反と認められやすい傾向にあります。
2.退職後の競業避止義務の定め・合意の有効性
従業員が退職後に競業行為をすることは原則として自由であり、退職後の競業避止義務はそれを定める就業規則の定めや個別の合意が要求され、その内容も合理性を欠くと無効となりました。退職後の競業避止義務の定めの有効性は、次の①~⑥の要素を総合考慮して、企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図るものとしてが適切かどうかの観点から判断される傾向にあります。
①守るべき企業の利益(競業避止の必要性)
技術情報、顧客情報、ノウハウ等守るべき企業の利益が、職業選択の自由を制限するに値するものであるかです。不正競争防止法の「営業秘密」(同法2Ⅵ)と同じように、秘密管理性、有用性、非公知性などが総合考慮されて判断されます。
もちろん、守るべき利益は、不正競争防止法上の「営業秘密」に限定されません。「営業秘密」として保護するのが難しい、独自のノウハウや技術的な秘密も、企業側の利益なり得ます。特約の中で保護すべき対象をできるだけ明確にしておきましょう。
②対象従業員等の地位
従業員全員を一律に対象とする規定や一定の役職以上を一律に対象する規定は、対象従業員の限定が不十分として無効となりかねません。あくまでも企業に営業秘密などを守る必要がなければいけませんから、対象の従業員は、機密性の高い情報に接する従業員に限定される傾向にあります(形式的な地位は問いません)。
なお、一般的な業務に関する知識・経験・技能を用いることにより実施される業務は競業避止義務違反の対象とならないとした裁判例もあります。また、対象の限定が不十分な就業規則の文言を合理的な内容に限定解釈して、その限りで有効性を認める裁判例もあります。
③地域的な限定
地域的な限定がないケースは否定的な報告に評価されます。他の要素との相関で判断されますので、会社が全国チェーンであるケースでは地域的限定なしに有効性が認められた例もあります。
いずれにせよ、無効となるリスクを低減するためには、従業員の不利益を考慮し、できるだけ地域を限定することになります。
④存続期間
1年ないし2年とする例が多いといわれています。
1年以内の存続期間は有効とされる傾向にありますが、2年の存続期間は否定的に評価する裁判例もあります。2年ぐらいからはリスクがあると考えた方がいいでしょう。2年を超える存続期間は、特に競業を禁止する必要があり十分な代償措置がある等の特別な事情がない限り、有効性を認めてもらうのは困難です。
⑤禁止される行為の範囲
競合他社への転職を全面的・抽象的に禁止する規定は、職業選択の自由を一般的に制限するものとして、無効と評価されかねません。他方、業務内容、職種、地域等を特定し、禁止する行為の範囲を限定すれば、肯定的な評価になります。例えば、対象行為を競業や在職中に担当した顧客との取引を禁じるに留めるケースでは有効と評価されやすいでしょう。
⑥代償措置
代償措置の有無については企業側の認識がないかもしれません。本来ある自由を制約するには対価が必要だということでしょうか。相当額の金員が交付されていれば、退職後の競業避止義務を課しても著しく授業員の不利益はないと評価され、有効性が認められやすくなります。退職後の競業避止義務に見合う代償措置がまったくないケースでは、有効性が否定されやすくなります。
退職金の加算、在職中の高額な賃金、特別な奨励金等、金員交付の名目は問われません。労務提供の対価を超える金員が交付されているケースでは、実質的に代償措置が講じられていると認められる可能性があります。
Ⅳ 取締役の競業避止義務
1.在任中の競業避止義務
取締役在任中の競業避止義務は法律で明確に定められています。取締役は会社のノウハウや顧客情報等を奪う形で会社の利益を害する危険が高いためと言われています。取締役が「自己または第三者のために」「株式会社の事業の部類に属する取引」をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社であれば取締役会)の承認を得なければなりません(会社法356Ⅰ①、365)。
「会社の事業に部類に属する取引」が競業です。会社が実際に行っている取引と目的物ないし事業(商品・役務の提供)および市場(地域・流通段階等)が競合する取引を意味します。定款所定の事業であっても実際に行われていない事業は対象外です。一方、会社が進出を予定しているときには対象となります。取締役が同業他社の業務執行をしない取締役となるだけでは対象となりません。部下や親族を役員に就任させて人的物的に援助を続けるなど事実上の主宰者として競合会社を支配していた場合には、自ら競業を行うのと同一視して競業避止義務違反となります。
なお、行為が「競業」に該当しなくても、営業秘密を利用して競業避止義務規定が守ろうとする法益を害する形で会社に現実に損害を生じさせたといえるケースでは、取締役の忠実義務違反の責任が生じます。取締役は、会社に対し、善管注意義務(民法644)・忠実義務(会社法355)を負います(両者は同じ意味と考えていいです)。競業避止義務は、善管注意義務・忠実義務の一内容となっています。
取締役が会社が関心を持つはずの新規事業機会等を自己の事業にすることも、会社に対する忠実義務違反となることがあります。会社の機会の奪取と呼ばれています。取締役が個人の資格で得た情報等をどこまで会社に提供するべきかは、会社のタイプおよび取締役の社内的立場等により異なり、たとえば、会社が上場会社等公開型のタイプであれば常勤の取締役はその能力すべてを会社に捧げるべき、将来の保障が必ずしもない中小企業の非同族の取締役にはそこまでの忠誠を期待することは無理である、と言われます。
「自己または第三者のために」とは、「自己または第三者の計算において」という意味(利益が誰に帰属するのかに着目)と考えられています。
競業の承認を得ないで取引をしたときは、当該取締役または第三者が得た利益の額を会社に生じた損害額と推定して損害賠償請求ができるという損害の推定規定が用意されています(会社法423ⅠⅡ)。会社の立証負担が軽減されます。
委任契約などにおいて、取締役等に対し、会社法の定める「競業」よりも広い形で競業避止義務を負担させている例も多いでしょう。禁止される事項と違反に対するペナルティを具体的に定めることはいいことです。
なお、退任予定の取締役による従業員の引き抜きもよく見られます。部下に対する退職勧誘が当然に忠実義務違反となるのではありません。職業選択の自由(転職の自由)の観点から、取締役の退任の事情、取締役と部下との従来の関係(自ら教育した部下か否か)、引き抜かれた人数等の会社に与える影響の度合い等の諸般の事情を総合考慮し、不当な態様のものに限って忠実義務違反になります。
2.退任後の競業避止義務
取締役の退任後の競業は、職業選択の自由、営業の自由の観点から、原則として自由です。従業員の場合と同様です。企業が役員に対して退任後の競業避止義務を負わせたいときには、委任契約や誓約書などで合意しなければいけません。競業避止義務の合意は取締役の職業選択の自由、営業の自由に関わります。そこで、社内での地位、営業秘密・得意先維持等の必要性、地域・期間など制限内容、代償措置等の諸要素を考慮し、必要性、相当性が認められる限りにおいて有効であると考えられています。
なお、競業行為が、在任中の営業秘密を利用した不正競争に当たる場合には、退任後であっても不正競争防止法違反となります。
Ⅴ 競業行為に対する措置
1.企業としての対処
①警告文競業行為が発覚し次第、当該従業員等に対して警告文を送付することが考えられます。
②懲戒処分
競業行為は就業規則違反(「会社の利益に反する著しく不都合な行為」など)となります。
退職前に競業行為が発覚した場合には、退職の申出を承認(正式受理)をせず、懲戒解雇等を検討することになるでしょう。
③退職金の減額・没収
退職金の減額・没収は、退職金規程等就業規則にその旨の明確な規定が存在することが必要です。
勿論、定めが有効ではなければいけません。規定の合理性と当該ケースへの適用の可否は、退職後の競業制限の必要性や範囲、競業行為の態様等に照らして判断されます。
④監査・調査
競業行為をした従業員が、会社を私物化して不正行為をしていたというケースは多々見ます。調査する必要があります。
⑤被害を抑える努力
早急に被害を食い止めなければなりません。法律的な対処では時間がかかりすぎるのは否めません。
取引先への事情説明を直ちに行い顧客奪取をできるだけ防ぐ、社内に対して会社の毅然とした態度を示し引き抜き行為を防ぐ等、傷口が拡がらないための対処が必要です。
⑥予防が大事
なお、競合行為への対処としてはその予防が一番であることは言うまでもありません。
経験上、日々のガバナンスが競業行為を防ぐと感じています。ガバナンスが効いている企業では競業行為を招く環境がありませんし、競業行為をすることも難しいでしょう。
いくつか考えていることを挙げます。従業員の自由に任せていた場合には、モラルハザードが生じて競業行為を生みがちです。権限分掌を明確にしておくべきです。従業員の士気が高い会社は、従業員の引き抜きができず、競業行為も困難となります。問題社員の放置はモラルハザードの原因です。対処を先送りしないようにしてください。担当者だけがつながっている取引先を作らないでください。経営者も取引先とつながっておけば顧客奪取はされません。
2.法的な対処
① 損害賠償競業避止義務違反は債務不履行です(不法行為も成立し得ます)から、損害賠償請求ができます(民法415)。
ただし、近時の裁判例では、退職後の競業避止特約に基づく損害賠償について、職業選択の自由に照らして、制限の期間・範囲を最小限にとどめることや一定の代償措置を求めるなど、厳しい態度をとる傾向にあると言われます。
使用者は、競業避止義務違反と相当因果関係のある損害を主張・立証します。相当因果関係ある損害の発生、および損害額の立証はときに困難です。競業行為がなかったら当然に受注していたと立証します。いかなる利益を逸失しているか具体的に金額を算定し、それが難しい場合には合理的な推計計算をします。
逸失利益の計算期間は、競業避止義務違反の影響から回復する(新たな顧客の獲得、人材の補填、営業の回復等)に足りる相当期間ですが、6カ月以内が多いといわれます。
民事訴訟法248条の規定が利用された裁判例もあります。賠償額の立証が極めて困難な場合に裁判所が相当な損害額を認定することができると定める規定です。
不正競争防止法違反のケースでは、同法5条の損害額の推定規定を利用できます。
以上を踏まえると、誓約書等の合意書面では、立証負担の軽減のため損害賠償額の予定(民法420)を盛り込むべきかと考えます。もちろん、有効と認められる定めでなければいけません。
なお、退職後の競業避止義務の存在が認められない場合であっても、職業選択の自由や自由競争の原理を逸脱する違法な態様での競業が行われたときは、使用者に対する不法行為(民法709)が成立しうるとされています(最判H22.3.25、事案では否定)。
② 差止め請求
競業避止義務を定める就業規則や個別の合意に競業の差止め条項が明記されているケースでは、同条項に基づいて差し止めを求めます。差止めは、競業主体に直接重大な不利益を課す措置です。差止め対象の行為は必要十分な期間に限定され、差止め期間も必要十分なものに限定される等、合理的なものでなければいけません。
合意がなく、不法行為を根拠に差し止めをする場合には、違法性が強度で、事後的な損害賠償では損害の回復が図れない場合に限定されるといわれます。
なお、不正競争防止法違反が認められるときは、同法3条1項に基づく差止め請求ができます。
Ⅵ 従業員の引き抜き
1.従業員の引き抜き
競業行為に伴って他の従業員が引き抜かれる事例は多々あります。企業は人材の育成に多大なコストを払っています。かつ、人材が抜けるとそれを回復するのは容易ではありません。企業規模によっては、突如従業員を引き抜かれてしまうと、事業の遂行自体を困難ならしめる影響を受けます。企業にとっては到底許せない行為です。しかしながら、労働市場における転職の自由も憲法上の価値から尊重されます。引き抜き行為を行うことは原則として違法ではありません。単なる勧誘の範囲を超え著しく背信的な方法で行われ社会的相当性を逸脱した場合、あるいは引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法・態様で行われた場合に限って、違法な勧誘行為と評価されます。
その判断に際しては、引き抜かれた従業員の会社における地位、引き抜かれた人数、引き抜きが会社に及ぼした影響、勧誘の方法・態様等の諸般の事情が考慮されます。大量の引き抜き、きわめて執拗な勧誘、地位を利用した勧誘、経営秘匿情報を用いた勧誘、虚偽情報を用いた勧誘などが該当し得るとされています。
2.引き抜き行為への対処
引き抜き行為の事実を把握した場合には警告文を送付します。社内にも会社の毅然とした態度を周知する必要があるでしょう。引き抜きは原則として自由な行為であるため、特別な事情がない限り、差止め請求はできません。
損害賠償請求ができるのも、引き抜き行為が違法と評価されるケースのみです。その場合、競合他社の不法行為責任(709、715、719等)も追及できる場合があります。引き抜かれた従業員も別途競業避止義務違反が問われ得ます。
引き抜き行為に対する法的な対処は特に悪質なケースに限られます。仮に損害賠償請求ができたとしても、事後的対処では事業への悪影響は避けられません。従業員のモラルを維持して引き抜きを防ぐ日頃の経営努力が大切になりますね。
Ⅶ 秘密保持義務
1.在職中の秘密保持義務
労働者は、労働契約の付随義務として、信義則上、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務を負います。役員についても、委任契約の付随義務として、同様の義務が認められるでしょう。
在職中の秘密保持義務は、当然の義務でありますが、多くの企業では、就業規則あるいは誓約書や秘密保持契約等の個別の合意書面にて、具体的にその内容が定められていると思います。効果的なものにするためには、対象となる秘密情報の範囲および違反した場合のペナルティはできるだけ具体的に定めるべきでしょう。
なお、取引先との秘密保持契約では、自社が負うのと同等の秘密保持義務を役員・従業員に負わせることが要求されている例は多いです。
在職中の秘密保持義務違反への対処としては、従業員に対する就業規則に基づく懲戒処分・解雇、あるいは債務不履行による損害賠償請求(民法415)が考えられます。もちろん、差止め請求も考えられます。
漏えい先の第三者が、当該従業員等が秘密保持義務を負っている事実を認識した上で漏えいさせたのであれば、第三者に対する損害賠償請求(民709)も可能です。
2.退職後の秘密保持義務
従業員は、退職後については、就業規則あるいは個別の合意がない限り、秘密保持義務を負いません。退職後・退任後の秘密保持義務を課すためには、就業規則の定めを整備し、あるいは個別の合意を交わす必要があります。役員も同様です。ただし、退職後であっても、信義則上、一定の範囲では引き続き秘密保持義務を負うとした裁判例もあります。
秘密保持の定めあるいは契約は、職業選択の自由、営業の自由を制約する側面がありますから、必要性・合理性を求められます。秘密保持の対象を明確に定めることが必要ですし、秘密の性質・範囲、秘密の価値、退職前の地位に照らし、内容が合理性であることが要求されます。
なお、不正競争防止法では退職の前後を問わず「営業秘密」が保護され、第三者にも主張でき、立証軽減措置も設けられています。その代わり、不正競争防止法で保護される「営業秘密」は認められるハードルが高いです。
これに対し、就業規則や合意による定められた秘密保持義務は、第三者に対する効力は原則なく、特別な立証軽減措置もありません。その代わり、対象となる企業秘密の範囲・種類を自由に決められます。また、違反に対するペナルティを、その有効性が認められる限りで柔軟に定めることができます。
Ⅷ 不正競争防止法
1.不正競争防止法による営業秘密の保護
重要な知的財産である秘密情報が不正に開示、使用されると、それ自体で大きなダメージを受けるとともに、信用問題にも発展しかねません。情報流出には民法上の不法行為(民法709)によっても対処ができるのですが、必ずしも十分ではないため、不正競争防止法で特に保護を強化しているのです。不正競争防止法は、「営業秘密」(法2Ⅵ)の不正な取得・使用・開示を「不正競争」(法2Ⅰ④~⑩)として規制しています。役員・従業員は、在職中・退職後を問わず、「営業秘密」を保持する義務を負い、これに違反すると不正競争防止法違反となります。
不正競争防止法違反に対しては、差止め(法3Ⅰ)、損害賠償(法4)、侵害行為を組成した物の廃棄・侵害行為に供した設備の除却(法3Ⅱ)、信用回復措置(法14)を請求することができます。
刑事罰として営業秘密侵害罪(法21)も用意されています。
被害回復を容易にするために、損害賠償の推定規定(法5)、立証負担の軽減(法5の2)の規定が用意されています。
不正競争防止法では「営業秘密」を強力に保護しています。競業行為、秘密保持義務違反行為が、不正競争防止法が使える案件であれば、まずは不正競争防止法違反を問うことになるでしょう。
2.営業秘密と認められる要件
営業上の秘密がすべて不正競争防止法で保護されるわけではありません。これは、経営者によって必須の知識です。すなわち、不正競争防止法の保護を受けるためには、侵害された情報が「営業秘密」であると認められる必要があります。そして、「営業秘密」と認められるには高いハードルがあります。「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上、又は営業上の情報であって。公然と知られていないもの」と定義されます(法2Ⅵ)。したがって、
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
の3つが要件となります。
そのうち秘密管理性は容易に認められません。否定する裁判例は多数あります。秘密管理性が認められるためには、保有企業に主観的に秘密にする意思があるだけでは足りません。情報が客観的にも秘密として管理されていなければなりません(客観的な秘密管理性)。
①情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限性)
②情報にアクセスした者に情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること(認識可能性)
の2つが判断要素とされています。
就業規則の規定や合意による秘密保持義務の設定は秘密管理性を肯定する方向の事情の1つになりましょう。もちろん規定や合意だけではなく、パスワードなどで技術的にアクセスの制限をする、秘密情報として特定して厳格に管理するなどの管理の徹底も必要となります。不正競争防止法による保護を受けられるように管理を徹底していれば、同時に、不正行為の予防にも繋がります。
裁判例では、客観的な秘密管理性を、情報の性質、情報の保有形態、情報を保有する企業の規模などの諸事情を総合考慮して合理的な管理がなされていたかどうかで判断しています。情報の種類や事業内容に応じた、適切かつ企業規模に見合った管理ということですが、具体的にどのような管理をすればいいかはケースバイケースで画一的に申し上げられません。参考となるものに、経済産業省が出している「営業秘密管理指針」があります。弁護士等の専門家に相談し、適切な対処を準備しておいてください。
Ⅸ まとめ
1.競業避止義務・秘密保持義務・不正競争防止法
在職・在任中の競業避止義務・秘密保持義務は当然に認められ、退職後・退任後の競業避止義務・秘密保持義務は原則として就業規則等の定めや個別の合意がなければ認められませんでした。いずれにせよ、競業避止義務・秘密保持義務とも、具体的に、詳細に定めておくことが肝要です。そして、退職後・退任後の競業避止義務・秘密保持義務の定めや合意は、合理的な内容と認められなければ無効とされました。就業規則の定めあるいは個別合意文書を作成するにあたっては、有効性を判断する際に考慮される各項目について、できるだけ無効となるリスクを低減できるような条項を吟味しましょう。
不正競争防止法の定める「営業秘密」を利用した不正競争に対しては、同法に救済を受けることができました。ただし、「営業秘密」として認められるには高いハードルがあります。日頃からの厳格な管理が肝要でした。
2.事前準備・予防が肝要
競業避止義務、秘密保持義務、不正競争が絡む紛争は珍しくありません。被害の回復には困難を伴うケースがあります。仮に金銭的な被害回復が実現しても、それだけではダメージは回復できません。企業としては、顕在化する可能性が相応になるリスクの1つとして、被害をできるだけ小さくする対処を事前に準備しなければいけません。もちろん、そのような事態が発生しないように予防をすることがより大切になります。
一度、①どのような情報、どのような技術、どのようなノウハウを守らないといけないか、②現状ではどのような管理をしているか、③担当者が競業他社に転職したり独立した場合にはどのような影響があるのか、④就業規則や合意文書ではどのような内容が決められているのかなどを見直してください。もちろん、専門家の助けを得て確認してください。リスクは法的に評価しなければいけません。
この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)
◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員准教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)
(なかた法律事務所) 2022年2月 2日 09:08
中小企業のM&A徹底解説
広島市の弁護士仲田誠一です。当職は、銀行や事業引継ぎ支援センター等と連携するなどして、M&Aのお手伝いをすることが多いです。中小企業のM&Aは事業承継問題の解決方法の1つとして数が増えています。今回は、当職の経験に基づき、中小企業に特化したM&Aの解説をさせていただきます。
目次
M&Aとは事業承継との関係
株式譲渡
事業譲渡
方法の選択基準
価格の考え方
M&Aの流れ
その他の注意点
M&Aの費用
弁護士によるM&Aサポート
まとめ
M&Aとは
1.M&Aとは
M&Aは Mergers and Acquisitions の略称です。「合併と買収」と訳されるようですが、企業や事業の買収を広く意味する言葉として使用されています。資本提携や業務提携も含めることがあります。ここでは会社あるいは事業を直接あるいは間接に売り買いするケース(法人あるいは事業のオーナーを変更すること)を指す意味でM&Aを捉えます。
そのような意味でのM&Aの手法には様々なものがあります。
株式譲渡、株式移転、会社分割、合併、事業譲渡でしょうか。法的には株式譲渡の一種ですがTOB(株式公開買付)やMBO(マネジメントバイアウト)という手法もニュースなどでお聞きになっていると思います。
2.中小企業のM&Aの手法
中小企業のM&Aの手法は、ほぼ株式譲渡か事業譲渡の2つに収斂されます。法律上は、会社の所有者は株主です。財団法人等持分権のある社員がいない特殊な法人は別として、各種法人も同様出資者の所有物です。会社・法人が欲しければ、あるいは売りたければ、株式や出資金を売り買いすればいいですね。
それを端的に実現するのが株式譲渡です。従業員や役員が株式を買い取るケースはMBOと呼ばれることもありますが、その実質は株式譲渡の手法です。TOBは株式公開会社のお話です。
会社・法人そのものではなく、ある部門あるいはある事業だけを売り買いしたいケースもあります。そのケースでは当事者が合意する内容の事業だけを売買すればいいことになります。
それを端的に実現するのが事業譲渡ですね。
そして、中小企業のM&Aはコスト面の配慮も重要です。手間、期間、費用はできるだけ節減したいですね。株式譲渡あるいは事業譲渡は、他の手法と比べて手続が簡便となっています。
そのため、中小企業のM&Aには、株式譲渡、事業譲渡が利用されるのです。当職も年に数件はM&Aに携わっておりますが、株式譲渡か事業譲渡のスキームがほとんどです。
株式移転、会社分割、合併は、特殊なニーズがあるケースに採用すべき手法ですが、通常の中小企業のM&Aにはあまりそのニーズがありません。
合併は昔はよく利用されていたかもしれません。今では、税制上のメリットがほぼなくなり、コストがかかるだけの手法となってしまった感があります。税制上のメリットが大きい適格合併の場合を除いて選択するケースは少ないでしょう。
いずれにせよ、買い手・売り手双方のニーズに適した手続を選択することが効率的です。
手続選択から弁護士等の専門家にご相談されることをお薦めします。当事者は合併を考えていたところ、当職が双方のニーズを確認した結果、事業譲渡の手法で簡便かつ効率的に進められた、というような例は珍しくありません。
事業承継との関係
1.中小企業の事業承継
同族中小企業に必ず発生する、かつ最も大きなリスクが事業承継問題です。株式を公開している大企業は株主と経営者が別ですね。会社の所有者である株主は不特定多数、経営者は雇われ経営者です。会社法が前提とする「所有と経営の分離」が実現している状態です。経営者が引退したり、経営者の相続が発生しても、社長が交替するだけで、会社は問題なく存続していきます。
これに対し、同族中小企業では、会社の所有者である株主(1人あるいはその親族)と経営者が同じです。「所有と経営の分離」がなされていません。経営者が引退あるいは相続は、経営者=株主の変更となります。スムーズに事業=株式を引き継ぐ必要があります。同族中小企業の経営者=株主には、いつかは引退あるいは相続が発生しますから、同族中小企業では必ず事業承継が発生するのです。
後継者にスムーズに株式と経営を承継をしていかないと、会社の経営継続自体が危機に晒されます。これが事業承継問題です。中小企業=会社ですね。経営者の交替は技術面、人事面、営業面等経営に大きな影響を与えます。また、相続税の問題が発生することは勿論、後継者に株式が集中できなければ会社を所有し経営を継続することもできません。相続争いが発生すると、株主総会を開いて新しい役員を選任することもできない事態になりかねません。
一方で、事業承継問題はチャンスでもあります。経営者の交替によって事業が傾く例を耳にしたことがあるでしょう。銀行勤務の経験あるいは弁護士としての経験からは、企業再生が必要になる会社あるいは破たんする会社では、事業承継に失敗したことが経営悪化の要因の1つになっている例が多いと感じます。事業承継に成功した会社は、それだけでライバル企業に差をつけらます。
事業承継問題は死活問題ですから、現在、早めの対策の必要性が盛んに喧伝されています。
もっとも、事業承継対策と銘打っても、株式の移転等に絡む相続税対策がメインではないでしょうか。それは事業承継対策の一部にすぎません。
財産面の問題だけでも、相続税対策だけではなく、後継者への所得移転、株式の集中プラン等、所得税、法人税も含めたが税制の横断的理解に基づくプランニングが必要です。適切な事業の引継ぎを法律的に準備する必要もあります(株式の集中策、種類株や属人的株式による議決権の集中策、承継財産の整理・相続法対策、定款変更等による組織改革、人事制度改革など)。そして、何よりも大切な対策は、後継者の育成です。経営力を身に付け経営革新を行える後継者を育て、事業承継を機に中小企業の強みである経営のスピードを向上させ、会社を時流に乗せなければなりません。事業承継の解決には総合的な対策が必要です。
当職が事業承継対策をサポートさせていただくときも、連携する税理士と共に、場合によっては当職も一員として中小企業をサポートしている合同会社RYDEENが主催する後継者育成経営塾を絡め、ワンストップでの総合的なプランニングをさせていただくことがあります。
2.事業承継とM&A
事業承継対策は後継者候補がいることが前提となっています。しかし、後継者がいない中小企業の数は多く、当事務所のある広島県や隣県の山口県は後継者不在率が全国ワーストの部類に属しております。
会社の営む事業にはそれ自体社会的価値があります。中小企業は、日本の経済、特に地域経済を支える重要な存在です。事業をなくしてしまうのは社会的損失です。
また、従業員ほかの利害関係者も多数存在します。事業を引き継ぐのは経営者の責任とも言いうるでしょう。
そこで、M&Aです。後継者のいる同族中小企業は事業承継対策(親族内承継)で、後継者のいない同族中小企業はM&A(第三者承継)で、事業をバトンタッチして、事業や従業員等を守るのです。
事業承継対策の一環としてのM&Aは、現在盛んに喧伝されています。国も中小企業の後継者不足に危機感を持っているのですね。当職がお手伝いさせていただいているM&Aも、事業承継対策の一環のものが多いです。
買い手の視点から見ると、会社を買うチャンス、すなわち顧客・市場を新たに獲得するチャンスが増えているといえます。デフレ下で市場の拡大が見込まれない中では、顧客・市場を拡大するもっとも有効な経営戦略の1つといえます。また、人材不足が叫ばれるようになってからは、人材の確保もM&Aの目的になるようになりました。
株式譲渡
1.株式譲渡によるM&A
中小企業のM&Aに利用されることの多い株式譲渡の主張を説明していきます。株式譲渡とは、文字どおり株式の譲渡です。会社の所有者は株主です。株式譲渡とは、オーナーチェンジですね。
株式譲渡に必要な手続は、
①株式譲渡契約書の締結
②譲渡承認決議(株主総会、取締役会)-中小企業のほとんどは株式譲渡制限会社です
③役員の変更決議(株主総会、取締役会)
が基本となります。
通常は、株式譲渡による譲渡所得税課税と退職金支給による退職所得課税の兼ね合いで、
④旧経営陣への退職金支給
も絡みます。
単純に会社の所有権(株式)を売買する複雑ではない手続なので、利用されるケースが多いです。
2.株式譲渡によるM&Aの特徴
株式譲渡によるM&Aの特徴をいくつか挙げます。【法人格をそのまま引き継ぐ】
株式譲渡では、会社の法人格(器)はそのまま存続し、会社の所有者=株主が変更されるだけです。株式譲渡によるM&Aの一番大きな特徴です。
この特徴によるメリットは、
①会社の名称、契約関係、債権債務関係はそのまま継続する(営業への影響が小さい)、
②会社と雇用契約を締結している従業員は株式譲渡の影響を受けない(従業員をそのまま引き継げる)、
③許認可や取引先との関係も、届出が必要なケースもありますが、そのまま利用・維持できます(許認可、取引先をスムーズに引き継げる)、
④所有不動産や自動車の登記、登録の変更の必要がない(手間と費用がかからない)、
といったところです。
一方で、デメリットとしては、法人格をそのまま引き継ぐため譲渡会社の保有するリスクや負債の遮断ができない点が挙げられます。コストがかかっても買収監査をきちんと経てリスクを点検しておく必要性が高いといえます。
【退職金支給によるプランニング】
株式譲渡では取締役、監査役等の役員が退任することがほとんどです。引継ぎ等で会社に残ってもらうケースでも、別途業務委託契約等を締結して協力してもらう形をとることが多いです。一定期間旧経営陣が役員で残るプランニングは例外的なケースになります(資格、登録の関係で必要なケースなど)。
旧株主が役員を退職する通常のケースでは、の退職金により最適なプランニングが可能です。売り手からすれば、退職金も株式譲渡代金も同じお金ですが、課税関係は退職所得課税、譲渡所得課税(通常は長期譲渡所得)と異なります。買収総額を割り振るバランスを考えて、効率的なプランニングをします。なお、買い手が会社であるケースでは、株式取得価格をできるだけ下げるために退職金に多くを割り振った方が喜ばれます。
【会社の清算の必要がない】
株式譲渡では、会社の清算を考える必要がありません。法人はそのままで株主が変わるだけです。旧オーナーは役員から退任すれば会社から手が離れることになります。
これに対し、事業譲渡では譲渡人会社は残り、事業だけ移りますね。全部の事業を譲渡したとしても、将来の会社の清算という課題が残ります。
【その他】
株式譲渡契約書は、金銭の授受が記載されていない通常のケースでは、印紙税の課税文書ではありません。
また、株式譲渡は消費税の課税取引ではありませんので、譲渡代金について消費税を考える必要はありません。
事業譲渡
1.事業譲渡によるM&A
中法企業のM&Aによく利用されるもう1つの手法である事業譲渡について説明します。事業譲渡とは、文字どおり、事業の譲渡です。個人事業も含めて規律する商法の表現では、営業の譲渡になります。一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡することを意味します。
難しい言い回しですが、機械や不動産等の財産の売買ではなく、会社等の営む事業の全部または一部の譲渡なんですね。事業譲渡は、一部の事業を売買する目的で、あるいは譲渡人会社の負債やリスクを切り離す目的で、よく利用される手法です。
事業譲渡に必要な手続は、
①事業譲渡契約書の締結
②株主総会の事業譲渡等承認決議(会社法467条)
と株式譲渡と同様に簡便な手続です。
ただし、株式譲渡と異なり、当然に契約関係等を引き継ぐことはできませんし、個々の財産について移転に必要な手続をしなければなりません。
2.事業譲渡によるM&Aの特徴
【譲渡対象を自由に選ぶことができる】事業譲渡の最大の特徴(メリット)は、譲渡の対象を自由に設定できることです。
対象資産を選択することができますし、事業の部門・取引先との取引関係などを基準に一部を切り取ることもできます。
自由度が高く様々なニーズに対応することができますが、譲渡内容を決める事業譲渡契約書は緻密に作成する必要があります。
【リスクを遮断することができる】
株式譲渡は、会社という器そのものを売買するため、譲受人は債務やリスクを負ったままの会社の新オーナーになるわけです。これに対し、事業譲渡における譲受人は、譲渡人が負う債務を承継せず(勿論、その旨譲渡契約書に明記します)、リスクも承継しません。事業のみを譲り受けることができます。事業譲渡の大きいメリットです。
【原則として商号は続用できない】
ただし、譲渡人の商号を譲受人が使い続けると、譲受人も譲渡人の営業によって生じた債務の弁済責任を負います(商法第17条第1項)。
そのため、事業譲渡では、譲渡人の商号を使って営業を継続することをしないのが通常です。商号を変更しないといけないとなると、取引先関係の引継ぎに苦労をすることもあるかもしれません。デメリットですね。
商号を続用しなければならないときは、譲受人がこのような責任を免れるため、譲渡後遅滞なく譲渡人の債務については責任を負わない旨を登記するか、あるいは譲渡人および譲受人から第三者に対しその旨の通知をします(商法第17条第2項)。
【従業員の引継ぎ】
譲渡事業に従事する従業員はあくまでも譲渡人と雇用契約を締結しており、引き継ぐには譲渡人からの退職、譲受人への新規就職という形になります。従業員の合意が必要なのは勿論、退職金制度がある場合には譲渡人が退職金を支払う必要が出てきます(個別契約で譲受人が従業員の在職年数等退職金債務を引き継ぐ形もあり得ます)。デメリットですね。
【取引先との関係、契約関係、許認可】
取引先との契約関係や債権債務、賃貸借契約関係など契約関係も当然には移転しません。相手方の同意を得て、契約上の地位の移転あるいは新規契約等の手続を踏む必要があります。
許認可についてもそのまま利用することはできません。該当許認可で定められた手続に従って、譲受人が新たに取得する、あるいは譲渡手続を承認してもらう等しなければいけません。こちらもデメリットです。
【その他】
事業譲渡契約書は印紙税法の課税文書です。契約書には印紙を貼付しなければなりません。
また、事業譲渡の対象には消費税の課税資産を含みますので、消費税も考慮しなければなりません。
事業譲渡では譲渡対象資産である不動産の移転登記、自動車の登録変更などをしなければなりません。
方法の選択基準
1.株式譲渡を選択するべきケース
中小企業のM&Aで株式譲渡の手法がもっとも多く使われると思います。特に次のようなケースでは株式譲渡を選択するべきといえます。【経営者が引退あるいは廃業を考えているケース】
経営者が引退、あるいは廃業を考えられているケースでは、原則株式譲渡の方法を選択するでしょう。
事業譲渡では、譲渡人の会社が残ります(譲渡代金は法人に入り、事業譲渡益には法人税課税されます)。引退、廃業のためには、別途会社の清算手続を考える必要があります。
勿論、負債やリスクの遮断を目的に事業譲渡が選択され、清算手続を別途行うケースもあります。
【許認可の引継ぎがメインの目的となるケース】
許認可ありきの事業法人のM&Aは、原則として、許認可の関係で被買収会社の法人格を活かせる株式譲渡を利用します。
株式譲渡では、法人格の移動はありませんので、法人格に付いている許認可はそのままです。役員や株主の変更について届出が必要なケースがあるというだけです。
これに対し、事業譲渡では譲渡人に許認可が付いているままですので、譲受人が新たな許認可を取得する等の手続を踏む必要があります。
【取引先との継続取引関係に価値があるケース】
取引先との継続取引関係の引継ぎはM&Aの重要な目的です。
株式譲渡であれば、法人格はそのままですので、法律上は取引先との契約関係に変更はありません。取引口座もそのままです。取引基本契約書などで役員、あるいは株主変更時の届出等の手続が定められていることがあるだけです。事実上、引継ぎには万全を尽くさなければいけませんことは当然ですが。
これに対し、事業譲渡では、取引先との取引関係の引継ぎは、取引先の同意が必要になります。新たな取引口座の開設が難しい場合は事業譲渡ではなく株式譲渡でしょう。
【従業員をスムーズに引き継ぎたいケース】
従業員を引き継ぐことはM&Aの主要目的の1つでしょう。
株式譲渡であれば、従業員との雇用契約関係には影響がありません。この観点から株式譲渡を選択することも多いです。勿論、経営者変更を契機に退職されないよう、新旧経営者からの十分な説明等が必要です。
これに対し、事業譲渡は、譲渡人と従業員との雇用関係は譲受人には引き継がれません。従業員の引継ぎには、従業員の退職、再就職が必要となります。譲渡人会社に発生する退職金の扱い(譲渡会社での支給の有無等)や移籍後の譲受人での待遇(現状を引き継ぐか譲受会社に合わせるか等)も問題になります。譲渡人には従業員の移転を促す努力義務や、従業員の移転が実現しなかった場合のペナルティを伴う義務を負ってもらうこともあります。
【商号続用をしたいケース】
株式譲渡では商号を続用することが通常です。取引先の関係等の維持を容易にするためですね。
これに対し、事業譲渡では、商号続用をしないことが基本です(リスクを負えれば商号続用もあり得ますが)。
【事業譲渡ではコスト負担が大きいケース】
事業譲渡では、権利の移転に別途対抗要件の具備や合意が必要になります。不動産の移転登記、自動車の登録変更、リースの契約名義変更、賃貸借の名義変更等々ですね、契約移行等の手間がかかることは勿論、登記費用等に多額の費用がかかることもあります。
株式譲渡では、所有関係・契約関係等もそのままで、経営者交替に伴い保証人の変更が必要なるぐらいです。ケースによっては事業譲渡の様々なコスト面の負担から、それらのない株式譲渡を利用することもあります。
2.事業譲渡を選択するべきケース
一方、中小企業のM&Aでは事業譲渡もよく選択されます。特に、次のようなケースでは事業譲渡を検討することになります。【売り手が事業継続を前提とするケース】
売り手が事業継続を前提とし、ある部門等を売却したいときは(選択と集中)、事業譲渡を選択します。
【株式の集中ができていないケース】
経営者及びその家族が全株式を保有しておらず、第三者が一部株式を保有しているケースでは株式譲渡によるM&Aは使えません。全部の株式の譲渡でなければ、買い手が見つかる可能性は低いです。
これに対して、事業譲渡は、承認決議ができる限りで可能です(ただし、反対株主の株式買取請求権の行使のリスクもあります)。
株式の集中ができていないケースでは、まずは第三者からの買取り、自己株式化、名義株の整理等、株式の集中を事前に図ることが肝要です。
【売り手のリスク、負債を引き継ぎたくないケース】
事業譲渡は、譲渡人のリスク、負債を引き継がない形でのM&Aが可能です。株式譲渡ではそれらを遮断することはできません。そのため、株式譲渡では、売り手会社に含有するリスクや負う債務などをきちんと監査しなければならないことが多いです(買収監査)。
売り手企業の財務内容が悪い、あるいは不審な点もあるというケースでは、事業譲渡にて譲渡人の負債・リスクを遮断する方法が適切かもしれません。その場合には買収監査を簡便にすることもできますね。
【売り手の負債が多いケース】
売り手が債務過多である場合は、その負債を引き継ぐほどの株式価値がある企業はあまり存在しません。株式譲渡は使えないですね(合併も同じことがいえます)。これに対し、事業譲渡では、売り手の債務を引き離して事業だけを買収することが可能です(会社分割を利用しても可能ですが)。
ただし、売り手企業が倒産するほどの状況下での事業譲渡にはリスクがあります。経済的危機状況でのM&Aは、倒産手続等において、資産隠し、債務飛ばしと問題視され得ます。譲渡人の債権者から債権者取消権を行使される、あるいは破産管財人等から否認権を行使されるリスクですね。
そのような可能性のあるM&Aは、弁護士の関与の下で行い、適正対価であることと、適正な対価の使い方をしているということを、合理的に説明できる手順を踏む必要があります。
買収価格の考え方
1.買収価格の考え方
買収価格は、勿論ケースバイケースで決めることになります。需要と供給の問題ですからね。価格は当事者が自由に決めることができるのであり、決まりはありません。不当に安いあるい高いケースで税務上のリスクが発生することがあるだけです。
勿論、価格の目安というものはあります。
株式譲渡では株式の価値ですね。時価です。贈与税・相続税のための評価である相続税評価額は時価ではありません。
事業譲渡では事業(移転する財産も含めて)の時価ですね。
価値の評価方法はいくつかありますが、同族中小企業のM&Aでは、
① 時価純資産額
② 営業権価格
③ ①+②
を目安に考えることが多いです。同じパターンでもその具体的な評価方法は多岐に分かれます。
なお、当職がお手伝いする案件の中には、当事者間で既に譲渡価格はざっくりいくらと合意されていることも珍しくはありません。
税法上リスクが高い金額でない限りはそのまま話を進め、支払名目(代金か退職金か等)をアドバイスします。
2.買収価格の補足
前述した①資産価格、②営業権価格、③資産価格+営業権価格について、考え方を補足いたします。【資産価格(時価純資産)】
株式譲渡における時価純資産は、株式が表章する会社のモノ・カネの価値です。決算書あるいは試算表の純資産額をベースに、含み益をプラス、含み損をマイナス、換価価値のない資産項目をマイナス等するなど修正して算出します。例えば、決算上純資産(資本の部)が3000万円あるとして、不動産の含み損が1000万円、保険解約返戻金の含み益500万円あれば、時価純資産は2500万円です。
この純資産価格ベースだけでの価格決定も珍しくありません。利益が出ていない会社の営業権価格は考える必要がないですから。
事業譲渡では、譲渡対象とする資産の時価を算出いたします。金額が小さい物については簿価を利用するケースもあります。
【営業権価格】
営業権価格は、会社(事業)が将来生む利益あるいはキャッシュフローを買収価格に反映させるものです。換価価値のある資産がほとんどない会社であれば営業権価格だけで買収価額が決められますね。
営業権価格は、 ①基準とする利益 × ②算定期間(1~5年) で算出します。
①の基準利益には、営業利益、経常利益あるいは当期利益の直近2~3年の平均額を入れます。
営業利益の平均にて算出することが多いでしょうか、営業権の価格ですからね。
ただし、営業利益には、実際に支出されない費用である減価償却費を加えることが多いです。現オーナーの役員報酬が大きい場合には買収後想定できる役員報酬との差額を加えることも多いです。
②の年数に決まりはありません。3年分がスタンダードですが、業種や業態等により異なります。
安定した業種・業態なら3年より長い場合もありますし、不安定であれば短い場合もあります。
事業譲渡での営業権価格の算出はやや難しいですね。部門別の損益計算書等の数字を出してもらうのですが、販売管理費の振り分けが難しいです。また、看板を変えることのリスク、従業員を引き継げるかのリスク、取引関係を引き継げるかのリスクは、価格引き下げ要因となるでしょう。
なお、業種によって特殊な価格算定が慣例になっていることがあります。例えば、当職が経験したものでは、売上〇カ月分と決めるケース、タクシー会社で営業権付車両台数×単価で決めるケースがありました。
【資産価格+営業権価格】
時価純資産価額と営業権価額の合計額を買収額の目安とするパターンです。
一般的な考え方だと思います。もっとも、当職がM&Aの交渉をしたケースでは、営業権価格の考慮を頑なに拒む某上場企業もいました。
【買収総額と買収額との関係】
主に株式譲渡のケースの話になりますが、旧経営者に対して退職所得が譲渡所得よりも有利な範囲で退職金を支給するケースでは買収総額と実際の買収額(株式譲渡代金)とはイコールではありません。
買収総額は退職金支給額と株式譲渡価格の合計になります。退職金を支給すればその分株式の純資産価格も減少しますからね。総額を決めたら、退職金額を検討し、その余を譲渡代金にする形です。
また、長期間にわたって旧経営陣による引継ぎが必要な業態であり、旧経営者にある程度高額の報酬を支払わなければならないケースでは、営業権価格を加味しないこともあるでしょう。営業権は引継ぎにより実現し、営業権価格は実質的に引継報酬により支払われる形ですね。
M&Aの流れ
1.一般的な流れ
単純化するとM&Aの流れは次のようなイメージでしょうか。②から⑤や⑦の順番は前後しますし省略されるものもあります。
① マッチング(相手方候補者の選定)
② 基本契約書の締結
③ デューデリジェンス(買収監査)、価格・条件交渉
④ 最終契約書作成
⑤ 法定手続、最終契約書締結
⑥ 決済
⑦ 引継ぎ
①マッチング
相手方候補者が見つからないとM&Aがスタートしません。
相手方候補者は、当事者が候補者を見つけてくるケースも珍しくはありません。M&A専業コンサルタント、事業引継ぎ支援センター、取引銀行あるいは銀行系コンサルタントが探してくることも多いでしょう。
当職もマッチングを実現したこともありますが、情報量では銀行さんに劣ります。銀行の保有する情報量を活用することは大事です。
②基本契約書の締結
独占交渉権付与と秘密保持契約を内容とする基本契約書を、交渉のスタートとして作成するケースも多いです。必須ではないですが、作成した方が双方が安心でしょう。
それまでに確定した交渉結果の内容も盛り込むこともあります。
③デューデリジェンス(買収監査)、価格・条件交渉
M&Aは、買収対象の株式(企業価値)あるいは事業自体にリスクが包含されている危険がありますし、手続面でのリスクもあります。程度の差こそありますが何かしらのデューデリジェンスあるいは監査を入れることが多いです。
価格算定のためのデューデリジェンス、財務・会計監査、法務監査などです。
価格・条件交渉を当事者だけで進めることはあまりお勧めしません。価格はある程度の相場観をベースに協議した方がいいですね。条件面は最終的に法律的に可能な形で最終契約書に落とし込む必要がありますので、客観的な専門家が仲立ちあるいは調整しながら具体化する方がいいでしょう。かつ、当事者間ではどうしても感情的になってしまう場面が出てきます(感情的な問題でM&Aが頓挫することは珍しくありません)ので、専門家の助言や調整が欲しいところです。
④最終契約書作成
M&Aには契約書を作成する必要があります。基本契約書に対して最終契約書と呼びます。
株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書ですね。契約書作成は法律の専門家である弁護士のサポートを得てください。
スキームによっては、引継ぎのための業務委託契約書、事業用不動産に関する不動産売買契約書や不動産賃貸契約書、あるいは旧経営者が残るケースの取締役委任契約書など、他の契約書の作成も必要になります。
⑤法定手続
M&Aには、法定手続が定められています。法定手続を履行しなければM&Aの効力が否定されることもあります。
M&Aの方法により、スキームにより、あるいは会社の組織体制によって、必要な手続が変わってきます。法定手続の検討の過程で問題点が判明することもあります。
契約書作成に専門家(特に弁護士)が入るケースでは、手続面のサポートも得られます。
⑥決済
株式譲渡、事業譲渡等の実行日ですね。
銀行の応接室にて、双方当事者と当職のようなアドバイザーが立会って決済することが多いです。買い手の銀行融資が絡むことも多いですね。
決済日には、印鑑、鍵等の引継ぎや必要な登記書類の作成も行います。
株式譲渡ではほぼ必ず、事業譲渡ではケースによって登記が必要です。その場合には司法書士の立会いもお願いすることがあります。
⑦引継ぎ
引継ぎは、基本契約書締結から順次するケース、最終契約書締結から始めるケース、決済日から始めるケースがありえます。
引継ぎが必要な点や量は被買収会社あるいは事業の内容によって千差万別です。ケースバイケースで適切な引継ぎ方法を考えることも、M&A成功の秘訣になります。
旧代表者等が数か月から半年程度、業務委託契約に基づいて引継ぎや従業員へのケアをしていくことも珍しくはありません。
2.株式譲渡、事業譲渡の補足
【株式譲渡の流れに関する補足】株式譲渡では、リスクや負債を負っている会社の株式を売買します。そのためデューデリジェンスやリスク監査が重要となります。
しかし、価格がほぼ決まっているから税理士等による価格算定のためのデューデリジェンスは必要がない、企業規模や事業形態から税理士等による財務・会計監査までは必要がない、というケースも多いです。
それでも、法務監査は必ず入れた方がいいです。複雑な契約ごとですし、最低限簡便なリスク監査は必要でしょう(法務監査の中で、価格算定や財務面も最低限見てもらうというパターンも多いでしょうか)。
旧経営者との間の債権債務関係の清算も決済までに行います。旧経営陣との間の債権債務関係を残すのは得策ではないですからね。場合によっては、旧経営陣に対する債務を免除してもらい整理することもあります。繰越欠損があるケースですね、そうでなければ法人税課税があります。
そのほかにも整理できるものは整理してシンプルな形にして株式を売買することが多いです。
なお、引継ぎ関係の話では、株式譲渡では会社の契約関係には影響がないため、各種契約の旧代表者の連帯保証を新代表者に変更することも必要ですね。
【事業譲渡の流れに関する補足】
事業譲渡では契約書と引継ぎが特に重要になります。
事業譲渡の内容は契約書の記載次第ということになります。契約書の内容に一番気を使うことになります。
譲渡資産の切り取り、事業の切り取りを、漏れなく、かつ明確に記載しなければいけません。売掛金と買掛金をどう割り振るか、営業用電話やFAXの番号の引継ぎの有無等の細かい取り決めも必要です。
従業員の引継ぎが最大の関心事であることもあります。実行日前から従業員に対する説明、説得を重ねて、実行日に譲受人に再就職してもらうように手配しなければいけません。名目は別として、再就職時の手当(サイインインボーナス)を支給することもあります。
譲渡事業に必要な賃貸借契約等の契約関係の引継ぎも事前に相手方から了承をとって速やかに変更できるようにしておかなければなりません。
不動産や自動車など登記・登録が必要な資産の譲渡では実行日に変更登記等に必要な書類を授受します。
その他の注意点
1.契約、法定手続等の注意点
M&Aは、会社あるいは事業の引継ぎですので、ケースに応じて様々な課題が生じてきます。個々の事例に即して、譲渡対象会社あるいは事業の内容を把握し、当事者双方の意向を確認しながら、リスクの有無や問題点を洗い出し、調整しながら法律的に有効な形で契約条項を作成する必要があります。
注意点はケースに応じて多岐にわたるのですが、ここでは共通項と思われる点をいくつか挙げます。
【株主、株券の確認】
株式譲渡では、自社株式の保有状況の確認が必要です。決算申告書の附票は証明資料にはなりません。
会社成立時から現在までの株主の移動を説明できるようにしないといけないのですが、株主総会議事録等の古い書類が残っていないケースもあり、ケースバイケースの確認になります。
名義株式や第三者の保有株式がある場合にはできるだけ早めにその解消方法を検討しなければなりません。
事業譲渡でも、きちんと株主総会決議ができるのか、反対株主への対応が可能なのかを検討しなければなりません。
また、株券の発行の有無、発行会社であれば株券の存否を予め確認しなければいけません。株券発行会社かどうかは商業登記、定款で確認します。
株券発行会社であっても実際には株券を発行していないケースも珍しくありません。
株券が発行されていて現在見当たらないケースは一番困ります、失権手続等の手当が必要なのかを検討しなければなりません。
早期に状況を確認してできる手当を講じることが肝要です。
【資産の整理】
同族中小企業では、事業用の不動産等が会社所有ではなく個人所有であるケース、逆に会社保有資産を個人で使用しているケースも珍しくありません。
M&Aではそれらを整理しなければなりません。
個人所有の事業用資産(引き続き必要なもの)がある場合には、事業に引き続き使えるようにしなければなりません。新オーナーあるいは会社が売買等で引き継ぐか、所有者から賃貸借契約等で使用権を設定してもらいます。
所有者に対する貸付金が会社にある場合には代物弁済で整理することもありました。
会社保有資産の個人使用のケースでは、譲渡日に買い取ってもらうのか、退職金の現物支給として名義を変更するのか、会社から個人への移転名目を考えます。
引継期間があるケースではその間の使用を許可し、終了後に清算を考えるということもあります。
【不動産】
不動産の境界確定義務を定めるのか定めないのか(争いがなく確認標・鋲があれば問題はないのでしょう)、建築確認済書類等建築図書、検査済証が引き継げるかどうかも、確認をしておかなければなりません。
それらを欠くと買い手が増改築のときに困りトラブルになることがあります。保健所が絡む工場や薬局などでは、建物図面や届出書類の引継ぎも必要となってきます。
【許認可】
許認可の内容、移転手続の要否等は実行日前に余裕をもって確認をする必要があります。譲渡人に所管の役所にて確認をしていただくことが多いでしょう。
【役員保険】
役員退職金を手当てする等の目的で役員を被保険者として保険契約しているケースも多く、そのケースでは解約して退職金を支払うことで整理します。保険の解約時期と退職金支給決定等保険の解約益と退職金計上損金が期をまたいでしまうと無駄な法人税がかかってしまいます。
旧役員が引き継ぎたい保険がある場合には、保険商品が許す限り、個人の契約者の名義変更をします。法形式は、解約返戻金額を評価額とする退職金の現物支給あるいは売買によります。そうでなければ高い税金がかかります。名義変更のタイミングを間違えないようにしないといけません。
2.引継ぎの注意点
M&Aでは、契約書を作って法定手続を踏んで実行したら終わりではありません。スムーズかつ十分な引継ぎがなされなければM&Aの目的は絵に描いた餅になりかねません。引継ぎに関してもいくつかコメントをさせていただきます。
【旧経営陣の処遇】
事業譲渡であれば旧経営陣の処遇が問題になることはありませんが、株式譲渡であれば問題になります。
会社のオーナーが交代する以上、旧経営陣は取締役等役員から退任してもらうのが原則です。けじめをつけることがスムーズな体制移行には必要です。従業員や取引先にも経営者が変わったことをきちんと認識してもらう必要があります。
ただし、一定期間取締役として役員報酬をもらうことが条件の案件や、建設業等資格の問題で旧経営陣に役員として留まってもらう案件もあります。
経営権の問題が曖昧になることや定款で定めた取締役任期の関係のリスク等の課題がありますので、慎重にプランニングしなければいけません。
【引継ぎの形態】
引継ぎが2~3日で終わるようなケースではいいのですが、取引先との取引関係を引き継ぐため、従業員に対するケアのため、あるいは技術移転が必要等のため、別途契約によって引継期間を設定することがあります。
そのうち、相応の引継業務が必要な場合には、業務委託契約を締結し、委託報酬を支払う形をとることが多いでしょう。期間雇用の形態をとるケースもあります。
なお、引継期間の報酬あるいは給与が相応に高額になるケースでは、営業権価格をその分割り引くことになるでしょう。
【経理、会計】
経理、会計の引継ぎ方法も決めなければなりません。きりがいい形で譲渡実行日を決算期末に合わせることも多いでしょうか(税理士さんもそのタイミングで変えやすいです)。
ただ、その場合は決算申告事務の引継ぎの問題が発生しますね。また、会計ソフトのデータは汎用性があることが多いですが、実際にデータを引き継げるかどうか確認も必要でしょう。
なお、取引先との受発注システムの引継ぎも苦労したケースがあります。薬局関係のレセプト等データも同様です。
【取引先】
取引先の引継ぎは一番大事ですね。ある程度余裕をもって新旧社長が挨拶に行くことをお薦めしております。
取引基本契約書のチェンジオブコントロール条項(会社の支配権の移動がある場合の届出あるいは承認を定めた条項)の有無も確認しないといけません。
なお、取引先の安心を得るために一定期間の引継ぎ期間をとり、旧経営者に補佐してもらうことも珍しくありません。
M&A費用
1.サポート費用
M&Aのサポートは様々なところから受けることができます。どこに依頼するか、どの範囲を依頼するのかにより費用は大きく変わります。一概に説明することは困難です。マッチング(相手先探し)からのサポートをするM&Aコンサルタント会社の報酬は、売買価格の〇パーセントで最低〇円と定まっていると思います。最低報酬は安くて5百万円から高くて数千万(想定規模によって違う)が多いのではないでしょうか。銀行系コンサルタント会社は報酬500万円からが相場でしょうか。これらと別に弁護士費用、税理士あるいは会計士費用がかかるケースもあります。
マッチングがなければM&Aはスタートしませんから、マッチングの対価として相応の費用を取ることは当然です。ただ、あまり高額だと地方の中小企業では利用できませんね。事業引継ぎ支援センターの利用も増えているようです。
当職は、マッチングをした地方銀行あるいは事業引継ぎ支援センターからの紹介により、マッチング以降のサポートをお手伝いをすることも多いです。地方銀行さんの持つ情報とネットワークは侮れません。地方の中小企業規模のM&Aは地方銀行のマッチングによるケースが多いです。当職自体もマッチングを実現したことがありますが、網羅的な情報を保有しているわけではない個々の法律事務所では限界があります。銀行さん等の手をお借りすることもあります。
ここでは、マッチング以外の、弁護士のサポートを受けるべきサービスの費用を説明します。
当事務所では、次のような目安で案件に応じた費用をいただいております。
【助言・契約書作成・法定手続のサポート】
スキームの設計、契約書作成、法定手続のサポートまでのサポートです。一貫して最後までサポートします、書類の作成だけではありません。
経験上、55万円(税込み)から165万円(税込み)の範囲で、事案や仕事量に応じて話し合って金額を設定しています。
金額設定は、買収規模、サポート項目に法務監査が入れるか入らないか、あるいは当事者双方から費用をいただけるか一方からだけか等の事情によって変わります。
なお、サポートの内容や他のコンサルタント会社の費用との比較からは高い設定ではなく、一応は良心的な部類に属すると評価されています。
【税理士と連携する案件】
価格算定のためのデューデリジェンス、財務デューデリジェンス、会計監査を入れる案件では、税理士さんにも加わっていただいております。相応の規模と金額の案件に多いです。
簡便なものについては法務監査の中で対応をさせていただいておりますが、きちんと財務・会計をチェックするということであれば、弁護士だけでは対応できません。
経験上は、弁護士1人・税理士1名で対応できる案件は220万円(税込み)程度、税理士2名以上が必要な案件はそれ以上の設定をさせていただいております。
【コストの考え方】
確かに、専門家のサポートを受けるためには安くない費用がかかります。
しかし、M&Aは大きな売り物、買い物です。トラブルが生じた場合の損害や解決にかかるコストも大きいです。専門家のサポートにかかる費用は、安心して手続を進めるための保険のようなコストだと捉えてください。
必要なコストだということを前提に、取引の規模、想定されるリスクの大小で許容できるコストを考えて、その範囲でサポートを得ればいいと思います。当事者双方がコストを負担する形がとれれば、各当事者のコストは下がりますね。
なお、当事務所も、コストに応じたサポート内容を提案させていただいております。
【費用の頂き方】
設定金額にもよりますが、着手時一括払いのケースや、分割であると着手金50~70パーセント、成功報酬金30~50パーセントの割合でお支払いいただくことが多いでしょうか。
契約時に協議をして決めます。
株式譲渡では、株式譲渡は株主間の契約ですから、株主から費用をお支払いいただくのが原則です。もっとも、会社から費用をいただくケースもあります、事業承継対策のコンサルタントともいえますので、顧問税理士さんと相談していただき、ご希望に沿うようにしています。
事業譲渡のケースでは、売買の当事者である会社から費用をいただきます。
2.その他諸費用
株式譲渡では、役員変更登記が例外的なケースを除いて伴いますし、本店変更や会社の目的の変更等の登記事項を伴うケースもあります。その場合の登記費用の負担があります(司法書士報酬と登録免許税)。事業譲渡でも、不動産登記が絡むことがありますし、会社の目的変更が必要なケースもあるでしょう。不動産の登記は固定資産評価額によっては大きなコストとなりますのでご注意ください。
当事務所では、司法書士と連携して登記もサポートしております。契約書、定款あるいは議事録等、登記の基礎となる資料は当職が作成しますので、それらを司法書士に依頼するコストは省けます。
その他は、印紙代(株式譲渡では原則として必要ありません)、証明書等の取得費用ぐらいでしょうか。大きなコストは見当たりません。
弁護士によるM&Aサポート
1.弁護士のサポートの意味
M&Aには多かれ少なかれリスクが伴います。当事者だけで進めることはお薦めしません。弁護士の助けを得て進めるべきでしょう。【プランニング】
M&Aは定型的なものではなく、オーダーメイドでプランニングをすることが必要です。様々な当事者のニーズを法制度の中でできるだけ効率的に実現する形でM&Aを成功させなければいけません。
民法、会社法、税法等法律を横断的に理解して、法律の中で可能な限りの最適なプランニングをする必要があります。経験上、スキームの設計が一番難しく、かつM&A成功の秘訣であると感じております。
法律の専門家である弁護士のサポートを是非とも得て欲しい所以です。
【契約書】
各種契約書は、その内容に疑義がないように第三者の目を入れて契約書類を作成してください。M&Aの内容は勿論、M&A後の引継ぎ等にもトラブルが発生しないように想定できる課題を契約内容にしていかなければなりません。当事者が良好な関係であったとしても、曖昧な契約書を作成するのは後日のトラブルのもとです。後に問題を蒸し返すことができないように契約書を作成します。
特に事業譲渡は、契約内容によってその効果が定まります。契約内容は契約書の書き方次第です。
また、M&Aの当事者には、単なる売り買いの価格面ではなく、その他の条件面や引継面を始め、M&Aに関連して様々な想いや希望があります。それらニーズを法律に則った形で具体化し調整する、それらを契約書に盛り込む、あるいは別途合意書等の取り決めを行う等するサポートが必要です。
是非とも、法律の専門家、トラブル事例を熟知している弁護士のサポートを得てください。
【法定手続】
M&Aには各種手続に伴い必要な法定手続があります。それらを踏んでいないケースも見受けられます。トラブルのもとですし、M&Aの有効性に疑義も生じてしまうことです。
法律の専門家である弁護士のサポートにより安心して、かつ効率的に進めてください。
極端なケースでは口頭で取り決めをして法定手続を全く踏んでいないM&Aのケースの解決の訴訟代理人をした経験があります。きちんと手続を踏むことがトラブルの防止になります。
【リスクの監査】
M&Aでは多かれ少なかれ譲渡人が抱えるリスクを引き継ぐことになります。
株式譲渡(合併もです。)は、被買収会社のリスクはそのまま残りますので、リスクの監査を経ることが望ましいです。
事業譲渡であれば譲渡会社の抱えるリスクはある程度遮断できますが、それらリスクは事業価値自体の評価にかかわります。
リスクは、最終的に法律を経て(裁判等)、損害賠償請求権等の形で顕在化しますので、監査は弁護士が法的な観点からするべきです。買収監査をどこまでやるかどうかはコストとの兼ね合いですが、少なくとも最低限の法務監査は弁護士にしてもらいましょう。
【総合的なサポート】
M&Aには、総合的なサポートが必要な事案もあります。
財務デューデリジェンスが必要な案件はぜひとも、そうでなくとも退職金が絡む税務面での設計はその限りで、税理士の助けが必要です。司法書士の助けも必要でしょう。実行後速やかな登記が必要になります。一番の理想は、ワンストップでそれら専門家のサポートを得ることですね。
当職の場合も、税務的なアドバイスが必要なケースでは(税法も大学院の客員准教授として税法を担当しておりますが)税理士に相談し、あるいは登記面で司法書士のアドバイスを得ながらサポートをすることが多いです。
弁護士、税理士がタッグを組んで取り組まなければならない財務デューデリジェンス等が絡む案件では、連携する税理士にも入ってもらいます。
なお、中小企業サポートの目的で士業(弁護士、税理士、司法書士等)が集結した合同会社RYDEENの一員として総合的なサポートをすることも多いです。
【M&Aに精通した弁護士のサポート】
弁護士業務の中でM&Aはやや特殊な部類の仕事になります。専門的な知識は前提として、様々なケースに対応できるだけの場数を踏まなければ十分なサポートができないかもしれません。
法律だけ知っていればいいわけではなく、得手不得手のある分野です。また、M&Aサポートに向けて他の士業との連携体制を整えていなければ総合的なサービスを提供することができません。
弁護士のサポートは必須と思いますが、どうせサポートを受けるのでしたら、M&Aに精通しサポート体制を整えている弁護士のサポートを得てください。
弁護士に相談する際には、弁護士に対して疑問点や質問等を投げて、具体的かつ的確な回答を得られるか、本当に任せてよいかをよく吟味して選択するべきでしょう。
手前味噌ですが、当職は、銀行勤務経験から会計にも明るく、税法にも精通しており、M&Aサポートの経験も数多く、他の士業との連携体制も整っております。ぜひ、ご相談ください。
2.サポートのタイミング等
弁護士がM&Aをお手伝いするタイミングは、①相手方候補者探し(マッチング)から
②相手方候補者との契約交渉の段階から(交渉あるいは調整、助言、スキーム設計)
③契約書作成の段階から(助言、スキーム設計、契約書作成、法定手続サポート)
とケースバイケースです。
また、関わり合い方も、一方当事者の代理人のケース、あるいは双方当事者のアドバイザーとして調整していくケース等、ニーズに合わせた形をとっています。
①当職の伝手でマッチングを実現した例もありますが、銀行のサポートを得ることもあります。
当職が携わるM&Aでは、①のマッチングは、当事者で既に話し合っている、あるいは銀行ないし事業引継ぎ支援センターが既にマッチングしているケースが多いです。
②相手方候補が決まっても、なかなか当事者間でスムーズに話し合いができないケースもあります。当事者では協議がし難い事柄もありますね。また、概要は合意できても、それを形にするスキーム作りはなかなかできません。
弁護士が一方の代理人あるいは双方のアドバイザーとなり交渉あるいは調整しながら整理をしていきます。弁護士のアドバイスを受けながら具体的に話を詰めていくだけでも大きな意味がありますね。
③ほぼ当事者で話が決まった段階で、契約書はきちんと作らないといけない、具体的にどう進めていいかわからない、客観的な第三者に入ってもらった方が安心だ、等の理由で弁護士を入れることも多いです。
当事者で決めた話を吟味してスキームを設計し、助言をしながら契約書の形に具現化していき、法定手続等もサポートします。
単に契約書を作ればいいわけではありません。どのように契約書を作るかが大事であり、手続の段取りを組んでスムーズに進めていくサポートが重要です。
②と③は重なり合います。③の場面でも、これまでの交渉結果を具体化するスキーム設計を改めてしなければなりませんし、交渉により確定しなければならない詳細が多く残っているが通常です。
また、②③の段階で、買収監査を盛り込むケースもあります。法務監査、財務デューデリジェンス(こちらは税理士と連携します。)ですね。
買収監査をサポート項目に入れない場合でも、契約書作成過程にて最低限の法的リスクのチェックは行っております。
どこで依頼するべきかはケースバイケースの判断でしょう。ただ、遅くとも相手方との具体的な交渉の段階では、少なくとも弁護士の助言を得る方が安心ですし効率的です。
なお、交渉自体は当事者の方がやりやすいという話をよく聞きます。一面真実ですが、契約ごとはシビアに接しなければならない場面もありますし、感情的になって決裂するケースも少なくありません。当事者で話し合いを進める際も、少なくとも専門家による整理をしながら進めるべきでしょう。
まとめ
1.中小企業のM&A
中小企業のM&Aに特化した形で、M&Aとは何か、事業承継の一環としてのM&Aの位置付け、特に利用が多い株式譲渡と事業譲渡、手続の選択基準、価格の考え方、M&Aの流れ、注意点あるいはM&Aにかかる費用などを説明させていただきました。網羅的な説明に終始し、詳細まで立ち入ることができなかった点は多々あります。また、M&Aは個々の事情に即したオーダーメイドの設計が必要ですので、そのすべてを解説することもできません。簡単にまとめると次のようなことになります。M&Aは事業承継の一環として、あるいは経営戦略として活用されています。中小企業では基本的には株式譲渡か事業譲渡の手法を選択します。ニーズに応じて株式譲渡と事業譲渡の特色に照らしてスキームを設計しなければいけません。価格の考え方自体も一律ではなく、売買・退職金・業務委託なども絡んできました。その他様々な注意点や課題もクリアして、スムーズな引継ぎを実現しなければなりません。専門家のサポート費用は必要なコストでした。
説明内容は概括的に留まっている感もありますが、しかしながら実務経験に応じた解説になっております。ご参考にしていただければ幸いです。
2.法律的あるいは総合的なサポート
M&Aでは、法律的にリスクを確認して、法律的に可能な形で当事者のニーズを具現化し、後の法的トラブルを防止する必要があります。法定手続を踏まなければならないことも当然です。M&A自体大きな買い物、売り物ですし、トラブルを生じさせてはその解決に多大なコストがかかる事柄です。弁護士による法律的なサポートがぜひとも必要です。
M&Aは専門的な分野であり場数を踏む必要がある事柄です。個々のケース毎に新たな課題が提示されてその都度解決策を講じていくようなイメージがあります。M&Aに精通した、かつサポート体制を整備した弁護士のサポートを得るべきでしょう。
勿論、当職は、M&Aに精通した弁護士の一人と自負しておりますし、業務の柱の1つとしてM&Aサポートを掲げて経験も積んでおります。他士業との連携体制も用意しております。M&Aをお考えの際には、ぜひともご相談ください。
この記事を書いた人
 弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)
弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
◆経歴
1996年4月~ あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~ 東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~ 広島大学大学院法務研究科
2008年12月 弁護士登録
2017年~各前期 広島大学大学院客員准教授(税法担当)
その他、広島市消費生活紛争調停委員会委員等
◆資格等
弁護士、公認内部監査人試験合格
(なかた法律事務所) 2020年5月29日 09:35
会社の自己破産の徹底解説
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。当事務所では、破産、民事再生などの倒産事件を業務の柱の1つとしております。
会社、法人破産は、業種、業態、現在の業況あるいは資金繰りなど、個々のケースに応じたオーダーメイド的な対応が必要となります。段取りが大事なのですね。
会社、法人の自己破産をご検討されている方へ、できるだけ共通項を探った解説をさせていただきます。目次
法人の破産とは法人の破産は最後の手段か
法人の破産の選択
弁護士に相談するタイミングなど
法人の破産の流れ
破産に必要な費用の目安・費用の捻出
取引先との関係は
従業員との関係は
準備にあたっての留意点
弁護士に依頼する意味(倒産弁護士)
まとめ
法人の自己破産とは
1.自己破産とは
簡単に申し上げると、破産手続は、資産・債務の清算手続です。破産開始決定時の資産を現金化し開始決定時の債権を弁済(配当)していくイメージです。実際には配当ができずに破産が終了する事件も多いです(「異時廃止事件」と呼ばれます)。
自己破産とは、破産手続開始の申立てを自分(法人・個人)が行う場合です。自己が破産の申立てをするから自己破産なのですね。破産というと僅かな例外を除いてほぼ自己破産に当たります。
他に、数は少ないですが、取締役、理事、業務執行社員あるいは清算人が申立てる「準自己破産」や、債権者が申し立てる「債権者申立て」の破産もあります。
債権者申立ての破産についても破産管財人として携わったことがありますが、広島本庁でも年数件あるかないかでしょうか。
2.法人と個人の自己破産との違い
法人の自己破産と個人(自然人)の自己破産は次のような違いがあります。◆法人破産には免責手続がありません◆
法人破産の場合には、手続完了により法人格が消滅します。そのため、破産手続が完了すれば債務を負う状態はなくなります。
これに対し、個人(自然人)の破産の場合には、破産をしても人格は残りますから、破産手続(財産負債の清算手続)を経ても清算後残った債務が残った状態になります。そのため、別途借金支払義務を免れるための「免責」手続が用意されています。
◆法人破産では必ず破産管財人が選任されます◆
法人破産では、必ず破産管財人が選任されます。破産管財人が財産の換価、配当等を行っていきます。いわゆる「管財事件」です。予納金が標準100万円と高額になります。破産手続開始決定により会社、法人の財産管理処分権は破産管財人に移行します。
これに対し、個人破産の場合には、破産管財人が選任されない事件(「同時廃止事件」といいます)の方が多いです。広島地方裁判所本庁では、個人破産のうち70パーセント前後が同時廃止事件でしょうか。同裁判所では、免責不許可事由の程度が大きいケース、過去5年以内に経営あるいは事業を行っているケース、明らかにオーバーローンと認められない不動産を所有しているケース、一定額の財産があるケース(預貯金50万円、その他の財産は項目毎に20万円)などに限り破産管財人が選任されます。
なお、法人破産と同時に法人代表者の個人破産を申し立てることが多いですが、代表者は上述の基準によって管財事件になります。
◆自由財産の有無◆
法人破産の場合には、法人の財産は原則すべからく換価されて残りません。法人格がなくなりますから。
一方、個人破産の場合には、自由財産拡張手続を経て裁判所の許可を得れば、一定の財産が手元に残すことができます。破産後の生活が保障される形です。
◆事業の整理◆
会社、法人破産の申立て準備は、程度の差こそあれ会社・事業の清算も進めなければならないことが特徴です。必要書類を揃えればいいだけで準備が済むことが多い個人(自然人)のケースと異なります。
法人の自己破産は最後の手段か
1.事業継続の可能性の見極め
会社・法人の営む事業はそれ自体に社会的価値が存在します。かつ、従業員さん、取引先など多様な利害関係者も存在します。その事業をなくしてしまうのは偲びないことですし、社会的な損失です。そのため、事業継続に悩まれる経営者の方は、まず金融機関のリスケジュール(条件変更)あるいはM&Aでの事業継続の可能性を見極めるべきでしょう。
例えば、金融債務の返済をストップすれば資金繰りが回るのであれば、リスケ中に経営改善を図ればいいわけです。
企業再生は、企業の収益力が維持あるいは向上されることが前提になります。再生協議会や銀行主導のリスケを経て破産に至った法人の破産管財人をすることもありますが、コストダウンに重点を置きすぎた安易な資産の切り売り、事業縮小は、多くは企業価値を毀損するだけで傷を深くするだけに終わる可能性が高いので慎重にするべきです。
また、企業価値あるいは事業価値がある事業のM&Aによる承継も考えられます。それだけでは負債の抜本的解決にはならないことが多いのですが事業は残りますね。経済的危機状態のM&Aは法的リスクも大きので慎重におこないます。
当職は、銀行で企業再生にも携わりました。事業継続の可能性の見極めからご相談ください。
また、現在は認定経営革新等支援機関でもあります。事業計画策定のお手伝い、リスケジュールのお手伝いもしております。M&Aのサポートも主業務の1つとしております。事業継続、M&Aも含めてご相談ください。
2.法人の自己破産は最後の手段か
会社、法人の自己破産は、上述のような意味では、最終手段といえるかもしれません。しかし、破産はぎりぎりまで引き延ばすべき手段でもありません。余力を全く残さない状態での破産は困難です。他の選択肢と並行して検討し、早期に決断しなければならない事柄です。その決断も大切な経営判断です。
◆破産費用の捻出◆
破産費用(弁護士費用・予納金)を用意できなくなれば破産もできません。
事業継続を引き延ばした結果として費用が用意できずに、会社の破産を断念された経営者さんもいらっしゃいます。
◆早期の決断も大事な経営判断◆
早期の決断が結果的に迷惑をかける範囲を拡げません。給与の未払いが残らない形での事業廃止ができるタイミングが望ましいです。
また、破産は利害関係者に対する最後のけじめとも言い得ます(夜逃げや休眠状態で放っておかれるよりは破産手続を望まれるのが通常です)。
◆経済的再建◆
経営者様とそのご家族の早期の生活再建も図らなければなりません。
経営者家族の生活を極限まで切り詰め、働き通しで体調を崩すなど苦労を重ねてきた末に弁護士に相談される方も多いです。その責任感には頭の下がる想いですが、「もう少し早くご相談に来ていただければ。」「そこまで思い詰める必要はなかったのではないか。」と思われる事例も多く目にします。
会社、法人の自己破産の選択
1.自己破産を選択するべきケース
金融機関のリスケで対処できるケースであれば自己破産を選択する必要はありません。あるいは、M&Aで事業自体は残す途も検討してよいでしょう。一次的な資金繰りの悪化を改善するだけで経営が持ち直す余地があるなら、金融機関のリスケジュール(条件変更)により資金繰り手当てができる限りで対応が可能です。金融機関の支援を受ける間に経営改善策の実施により経営が持ち直す見込み、計画が立てられるのであれば、また同様です。利払いのみのリスケをすれば資金繰りがある程度余裕をもって回る、かつリスケ期間中に金融機関への弁済計画が立つまでの経営改善を図る見込みが立ちそうだというケースでは、経営改善策を試すべきでしょう。経営改善計画や資金繰り表などを金融機関に提出し交渉をします。
例えば、設備投資等による債務過多が業績不振の主な原因であり、事業の収益力自体は相応に残っているケースでは、リスケ対応により資金繰りを改善しつつ計画的に債務を削減することで難局を乗り切れるでしょう。
しかしながら、企業の業績不振には多種多様な要因が絡みます。企業努力では如何ともしがたい外在的な要因も大きいです。単純明快かつ解決可能な原因による業績不振で簡単に改善できる、あるいは一時的に資金繰り手当てをすれば簡単に業績が持ち直すと計画が立案できるケースは少ないです。
リスケによる企業再生を図る際には、単なる時間稼ぎになってしまわないのかをよく吟味する必要があります。延命だけでは傷口が深くなる、あるいは拡がることになります。
企業再生あるいは事業再生には、事業自体の収益力がある、あるいは収益力が改善する見込みがある、ということが前提となります。慢性的な赤字体質であり事業継続をしても今後の状況を悪化させる、あるいは現在の厳しい状況が続くだけというケースでは、早い自己破産の決断が必要でしょう。金融債務の返済を一時ストップしても資金繰りが余裕をもって回らないケースでは、慢性的な赤字体質といえます。
経営者に企業再生への気力・体力が残っているかも重要な要素です。当職に相談に来られる経営者の方は経営努力をされた結果として現在に至っているのであり、疲弊されて余力も残っていないという方が多いです。
その責任感は尊敬されるべきです。結果として自己破産を選択しても非難されるものでは決してありません。
2.民事再生との違い
会社、法人がとる法的債務整理手段としては自己破産のほかに民事再生もあります(なお、大企業向けの会社更生という手続もあります)。民事再生は、債務を大幅に減額した上で、経営者の交替もなく事業を継続できるという大きなメリットがあります。
しかし、仕入先・外注先の協力が必要なこと(あるいは現金決済に耐えうるスポンサーが必要なこと)、事業用資産の担保権者の協力がいること、債務免除益の課税がなされること、及び申立てに多額の費用がかかること、という条件が揃わないと選択できません(事実上必要となる条件も含んでいます)。実際には、民事再生に適合するケースは少ないです。
弁護士に相談するタイミングなど
1.弁護士に相談、依頼するタイミング
弁護士に相談、依頼するタイミングは早いに越したことはありません。早めに弁護士に相談をし、金融機関へのリスケ要請、自己破産申立て、民事再生申立てなどの手続選択の方針を決定し、それに応じた準備をしていかなければなりません。
自己破産を選択するにも、費用の捻出の問題を始め、破産を前提として事業廃止に向けた準備を段取りを組んで進めることが理想です。
残された時間や、相談時の状況によって、できる準備や選択肢が異なります。
弁護士への依頼も、早期になされることが肝要です。会社・法人の自己破産では、事業整理に向けた段取りを計画的に組んで進める必要があります。段取りが悪いと混乱をいたしますし、破産法上問題となる行為がなされることがあります。準備段階での出来不出来が、後の手続に響くのです。
できるだけ早くから弁護士の指示を受け、あるいは弁護士のナビゲーションによりご準備をされた方が、効率的ですし、ご負担も小さくなります
◆相談時の注意点◆
弁護士への相談時には、少なくとも直近の決算申告書類一式をお持ちください(勿論、3期分程度を拝見した方が検討はしやすいです)。
資金繰表を作成されているのであればそれもお持ちいただいた方がありがたいです(資金繰り予想ができる入出金のメモ程度でもかまいません)。
連帯保証人の方の資産・負債状況もわかればありがたいです。会社、法人と連帯保証人である経営者を一体としての債務整理の方策を考えるべきです。
◆緊急の場合もあります◆
手形・小切手の不渡りが見込まれるなど急を要する場面もございます。
緊急の対応が必要なケースはそれに応じた対応をすることになりますが、1日が惜しいケースもありますのでやはり早めにご相談ください。
2.事業廃止のタイミング
破産手続をスムーズに進めるには事業廃止のタイミングが重要です。事業廃止のタイミングを間違えば、要らぬ混乱を招く、破産手続に移行することができないという事態を招きかねません。弁護士とよく相談の上で決めてください。事業廃止のタイミングは、買掛金等の支払いをストップすればお金が一番残る時点がベストになることが通常です。破産費用の手当てが必要ですし、残る財産は各債権者に平等に配当されるべきともいえます。
勿論、未払給与はできるだけないようにしたいところです。
事業廃止のタイミングの決定には、資金繰りのほかに、
銀行取引停止処分の時期
従業員解雇あるいは退職のタイミング(解雇予告手当の問題もあります)
資産整理の状況(弁護士関与の下で資産を処分して破産費用を用意することもあります)
も絡んでくる問題です。
事業形態によっては、新規の仕事を取らずに既存の仕事は時間をかけて順次止めていくほかないケースもあります。
ご事情に応じてベストなタイミングでの事業廃止を図ります。
法人の自己破産の流れ
1.会社、法人の自己破産の流れ(申立準備)
会社、法人の自己破産の相談~申立準備までの一般的な流れは次のようにイメージしてください。①方針・スケジュールの決定
方針と段取りを話し合い、事業廃止のタイミングをターゲットに定め、準備の段取りやスケジュールを立てていきます。
悩む必要はありません。弁護士の指示やサポートを受けて進めるだけです。
②受任通知の発送
弁護士との契約後、事業廃止のタイミングで受任通知を発送することがスタンダードでしょうか。債権者毎に受任通知発送のタイミングを図ることもあります。
受任通知が債権者に届いてからは、債権者対応はすべて弁護士が窓口になります。
勿論、既に取立てが厳しい、あるいは銀行取引停止処分が予定されているなど急を要する場合は早急に発送します。
③申立ての準備・事業の整理
会社、法人破産の申立て準備は、程度の差こそあれ会社・事業の清算も進めます。事業廃止の前後にわたり、例えば、従業員退職・解雇の手続、賃借物件の明渡し及び交渉、売掛金の入金先口座変更等売掛金の回収手立てをする、管理のための事業廃止時点の売掛金リスト・在庫リストの作成、債権者リスト作成、整理のための在庫や新規仕事の圧縮、財産の逸失を防ぐ資産保全、整理のための資産譲渡、継続的契約関係の解消(水道・電気を除く)、リース物件・所有権留保物件の返還、等々の準備をしていただくことになります。資産のうち簡単に現金化できるものは現金化をします(それにより破産費用を捻出することもあります、資産や在庫の処分、代金の管理等は必ず弁護士の関与の下で行ってください。後の破産手続に問題が生じることがあります)。
個々のケースで必要な準備は異なります。段取り、整理の程度、あるいは整理の方法など、すべて弁護士の指示を受けて負担なくご準備ください。その方が後々問題になりませんので弁護士としても安心です。
◆お金の管理◆
事業廃止時の現預金を弁護士に預けていただき、弁護士管理の下でどうしても必要なもののみに支出していくことが多いです。ある程度お手元に管理していただいて出納を記録してもらいながら、そこから事業の整理にかかる費用を支出していただくこともありますね。売掛金や貸付金の回収も弁護士が代理人として進めていきます。資産の処分代金も弁護士が管理します。
破産を見据えて、弁護士がお金を管理し、お金の散逸を防ぎ、適正な管理状況を報告できるようにすることが大事なのです。
④申立て
通常は、2か月~3か月程度の準備期間を経て、自己破産申立てを行います。
資産の整理及び売掛金の回収など段取りを組んだ事業の整理が終わるタイミングも待つことも多いです。
申立て先は、原則として、本店所在地を管轄する地方裁判所です。広島地方裁判所本庁ですと、民事第4部になります。
2.会社、法人の自己破産の流れ(申立て後)
申立て後の一般的な流れは次のようにイメージしてください。①破産開始決定まで
自己破産を申し立てると、裁判所から追加資料の提出や質問事項の回答を求められることがほとんどです。それを補正連絡と呼びます。
補正連絡に対応しつつ、裁判所から指示がある予納金を納めると、破産手続開始決定が出ます。
法人破産には必ず破産管財人が就任いたしますので、破産管財人候補者も同席する債務者審尋の日に破産開始決定が出ることが多いです。申立後1か月前後先がスタンダードでしょうか。
急を要する場合や債務者審尋が開かれない場合(最近増えています)では、予納金を納めるとすぐに破産開始決定が出ます。
②破産開始決定後~第1回債権者集会
破産開始決定が出ると、2~3か月に1度のペースで債権者集会などの期日が開かれます。代表者の方には、申立代理人弁護士と共に同期日に出席していただきます。
第1回の債権者集会までの間には、破産管財人弁護士の事務所に赴いて面談をする機会が数度設けられます。第1回の債権者集会の後は、破産管財人に呼ばれることはあまりありませんが、在庫や資産の処分などのため引き続き破産管財人から協力を求められることがあります。
③第2回債権者集会~
配当ができるまでの財産が形成されない場合、手続が異時廃止の形で終了します。配当ができる見込みがあるケースでは、債権調査、配当の手続がありますので、その分手続が長引きます。
第1回債権者集会が終わると、破産管財人からの聞き取り調査等はほとんどなくなります。期日に出頭する負担だけになりますので、それほど負担は大きくありません。
◆破産手続にかかる時間◆
一概には申し上げられません。不動産の処分や債権回収その他管財業務にかかる業務量にも依りますし、配当がなされる案件かどうかによっても所要期間が異なります。
資産の処分もない、配当もないケースでは3か月から6か月程度、それらがある場合には1年前後がスタンダードでしょうか。ただ、1年を超えるケースも珍しくはありません。
破産に必要な費用の目安、費用の捻出
1.破産に必要な費用の目安
破産に必要な費用は、弁護士に申立代理を依頼するための弁護士費用、申立時に裁判所へ納める予納金及び予納郵券です。◆裁判所へ納める予納金◆
裁判所に破産開始決定を出してもらうためには予納金を納めなければいけません。法人破産の場合は原則100万円です。大型管財と呼ばれる大規模な破産の場合にはより多額の予納金を要求されますし、休眠会社や資産の整理が必要のない会社等破産管財人の労力が相対的に少なく見積もられるケースでは交渉次第で減額も可能です。
なお、2社同時に申し立てると単純に倍となるわけではありません。
そのほか、裁判所が債権者等に書類を送る際に使用される予納郵券(債権者数に応じて納付します)がかかりますが、多額ではありません。
◆弁護士費用◆
弁護士を申立て代理人とする場合には、弁護士費用の手当が必要です。費用額は弁護士と相対での契約で決まりますので、定価はありません。費用の面の相談も弁護士相談の大きな目的の1つですので、お気軽にご相談ください(費用の面がご相談の大きな部分を占めているのが実情です)。
110万円(税込み)を確保できればありがたいです。一応の目安であり、必須というわけではありません。事情に応じて話し合いで設定しており、手間がかからないような案件ではより少額の金額設定もありますし、資産が相応にあるケースではより高額の金額設定もあります。
着手時に全額揃っている必要はなく、売掛金回収や資産売却などで捻出することもあります。
◆諸費用◆
多額ではないですが数万程度の諸費用もかかります。
◆余裕のある準備のためには◆
以上を踏まえて、当職は、法人1社の場合、トータル(弁護士と裁判所にかかる費用)で250万円を「目標」に準備していただくようお願いしています。
250万円用意できればある程度余裕をもって準備ができるという意味の目標であり、必須という意味ではありません。
ご依頼時に全額揃っていなければいけないということではありません。費用の手当の可能性を探る、手当の段取りを組むことも相談内容です。
◆代表者個人破産との関係◆
連帯保証人となっている代表者の自己破産も同時に受任するケースがほとんどです。
個人の破産での裁判所の予納金は30万円前後がスタンダードですが、減額交渉ができるケースもあります。
弁護士費用は法人・個人トータルで調整しております。例えば、個人で多くいただける場合は法人の分を減らす、あるいは法人で多くいただける場合には個人はいただかないというようなこともしております。
2.破産費用の捻出をどうするか
破産費用の捻出はほぼ例外なく頭を悩ませる事項です。依頼時によく吟味をして段取りを組みます。すべてを説明できるわけではありませんので、概要をお話します。
◆口座のお金◆
まずは、事業廃止時点で会社、法人の口座にあるお金が基本ですね。
支払いをストップして一時的に資金が多く残るタイミング(多くはそれが事業廃止のタイミングともなります)で、残った資金を弁護士に預けていただくことが多いです。
その準備として、借入銀行口座から順次資金を移す、あるいは入金先口座を借り入れのない銀行に変更する必要もあるかもしれません。
破産法は、債権者平等原則が理念となっております。支払いをストップさせてお金を移すことは、債権者の平等を期するための資産保全ですので、何ら問題がありません。
なお、取引先は勿論、租税公課や銀行も資金を確保しようとしますので段取りが大切になります。
◆弁護士に依頼した後に資金を捻出するケース◆
弁護士への依頼時に資金が揃っていなければならないわけではありません。売掛金回収、資産売却、金融資産の解約等で用意していただくこともあります。
弁護士関与の下で資産を現金化して破産費用に充てることは許されております。資金を弁護士が管理しつつ、その経過を裁判所にきちんと報告します。弁護士の関与なく資産を現金化して費消することは後に問題を生じさせる恐れがあります。
売掛金は、事業廃止後に、順次、依頼者が引き続きあるいは弁護士が回収し、回収金は弁護士が管理します。売掛金リストを作成していただき管理をしますね。滞納処分により売掛債権が差し押さえられると現金化ができなくなることには注意を要します。
資産を売却・換価することにより、費用の捻出をすることもあります。弁護士との相談時には、早期に換価できる財産がどれくらいあるのかも検討します。
取引先との関係は
1.買掛先への対応
相談者がよく悩まれることですね。仕入先、買掛先も、借入をされている金融機関と同様に、債権者です。弁護士が受任通知を発送した上で対応しますのでご安心ください。商品引き揚げの要請には応じられないのが基本です。後の破産手続で問題視される可能性もあるためです。在庫の所有権が仕入先にあることが契約書上明確である場合は返還することもあります。
買掛先からの取り付け騒ぎの危険もなくはありません。無断で商品等を引き上げることは厳密に言えば犯罪ですが、そのようなことが起きないよう、事業廃止時には事務所・倉庫や車などのセキュリティーにも気を付けていただきます。
場合によっては弁護士名の張り紙をして牽制をすることもあります。
混乱を避けるために弁護士名の受任通知を事業廃止の当日か翌日に届くように手配することも心掛けています。
2.売掛先への対応
販売先、売掛先は債務者の立場になりますので、事業廃止後も売掛金の回収を行わなければいけません。破産開始決定までに回収できなかった売掛金は、破産管財人が回収を図ります。事業廃止時の売掛金リストを作成していただき回収します(事業廃止したことを知ると支払いを渋る先も見受けられます)。
借入のある金融機関口座は弁護士の受任通知が届くと口座を凍結してしまい、基本的にその後の入金の引き出しには応じません。入金先を借入のない銀行口座あるいは弁護士口座へ振り込むよう依頼しなければなりません。
小口集金形態のご商売の場合には集金を引き続きお願いして回収するケースもあります。
在庫の処分を並行して行うこともありますね。
従業員との関係は
1.従業員の解雇・退職
残念ながら、事業廃止日が決まれば、従業員の方々を解雇する、あるいは従業員の方々に退職してもらうことになります。解雇には解雇予告手当が必要ない30日間の解雇予告手続をとることが多いでしょうが、ケースバイケースです。破産申立て準備にどうしても必要となる従業員がいらっしゃる場合(多くは経理担当でしょうか)、給料あるいは相応の費用をお支払いすることで引き続き残っていただくこともございます。
退職あるいは事業廃止に伴う社会保険、特別徴収住民税の異動手続、ハローワークの手続、源泉徴収票の発行等の退職に伴う手続は忘れないでください。
◆事業廃止をいつ従業員に伝えるか◆
事業廃止をいつ従業員さんにお伝えするかは悩ましい問題です。
従業員さんの生活等のことを考えると、できるだけ早くお伝えした方がいいとは思います(小規模会社であれば事情の説明により自主的に退職してもらえるケースも多いです)。
一方、あまりにも早く事業廃止を伝えると業務に支障を来すこともございます。
◆税理士・社会保険労務士
少し話はズレますが、税理士さんの協力が必要な場合もあります。費用との兼ね合いもありますが、事業廃止時点までは数字を作成してもらった方がありがたいです。
また、破産管財人が就任後に税理士に申告を依頼することもあります。
社会保険労務士さんがいらっしゃる場合には、退職手続等でご協力をいただくこともありますね。
2.未払給与等の扱い
賃金の未払いはないようにしたいと思われるのが経営者の常です。労働基準法上罰則も定められています。未払給与がない形で事業廃止できることが理想形ですが、支払えないケースがあるのも当然です。
◆破産手続における労働債権の扱い◆
労働債権は、破産手続開始決定前3か月間の未払給与と退職金の一部が財団債権として一般の債権者より優先して支払えることができます。
ただ、時間がかかりますし、支払えるだけの財産が破産手続の中で残るかどうかわかりません。また、事業廃止後できるだけ早く破産申立てをしなければいけませんね。
◆労働福祉事業団立替制度◆
そのため、労働福祉事業団立替制度の利用も考える必要があり、事業廃業時には従業員さんへの同制度の説明をするでしょう。
破産管財人の証明書の発行により未払い給与の8割が立替払いされますが、時間の制約があります。大まかに申し上げると、退職、解雇から6か月以内に破産申立てをしなければ対象になりませんので早期の破産申立てが必要になります(なお、破産手続外の認定制度もあります)。
賃金台帳、タイムカード、就業規則等、未払給与を確認できる資料も破産管財人に引継ぐことになります。
◆役員報酬の扱い◆
未払いの役員報酬は(従業員兼務役員のケースでは従業員分給料と認められ得る限りで別ですが)、一般の破産債権となります。経営者家族であっても従業員の立場のケースでは一般の従業員の給与と同じ扱いです。
◆中退金がある場合◆
退職金制度が中退共の場合は、請求手続をしていただければ(開始決定後は破産管財人が協力しますが)、従業員さんが受け取ることができます。
準備にあったっての留意点
1.やるべきことの整理をするべき
破産を準備するといっても、経験がある方ではない限り、何にどの順番で手を付けていいかわからず途方にくれるものと思います。また、破産をするためには事業の清算が必要ですが、どこまで清算すべきか事情により異なります。場当たり的な準備は、疲弊しますし、効率も悪く、中には後で問題となる行為をしてしまうこともあります。弁護士のサポートを受けて整理をしてください。
◆やるべきことの整理◆
準備の仕方や優先順位には勘所があります。様々な問題点や課題を整理してシンプルに段取りを組むのが弁護士の腕の見せ所です。
最低限必要なこと、できればやっておきたいこと、放っておいても仕方がないこと等々、やるべきことの整理をします。そうすれば全体像がつかめますし、優先順位も決めることができ、悩まずに準備ができます。
当職は、優先順位をつけたリストを作成し、それをチェックしながら打ち合わせを重ねています。
◆要望や問題点は早めに弁護士に伝える◆
なお、準備にあたって、様々なご要望もあることと思います。また、説明が難しい、準備が難しい等の問題点もあることが多いです。弁護士へは、早めにそれら要望や問題点を伝えてください。
破産法上問題がない形で、可能な限り、ご要望等を形にするよう心掛けています。問題点への退職も準備しなければいけません。遅くなるとそれだけ手当ができなくなる可能性が高くなります。
2.やってはいけないこともある
破産手続をスムーズに進行させるため、あるいは問題視されないためには、準備にあたってやってはいけないこともあります。◆書類の廃棄は慎重に◆
事業を廃止したからといっても、すべての書類の廃棄をするのは止めてください。破産手続の中で提出しなければならない書類も多々あります。
◆否認対象行為◆
否認対象行為を行ってはいけません。否認とは、破産管財人がその行為の効力を否定し財産等を取り戻す制度ですが、破産管財人が否認できる行為、その要件は破産法で定められています。主要なものだけ簡単に説明させていただきます。
偏頗弁済は否認の対象です。偏頗弁済とは支払停止状態等の経済的危機状態での不公平な債務の弁済です。問題となるのは、経営者家族、親族に対する弁済が多いです。弁済の相手、時期、債務の内容等によって判断が異なります。
事業廃止のタイミングも含め、支払っていいもの、いけないもの振り分けを弁護士と相談してください。
財産の散逸行為も否認の対象です。会社の資産の廉価売買、放棄など、財産を減少させる行為にお気を付けください。中には合理的な説明が可能なものもありますので、実行に移す前に弁護士に判断をしてもらってください。
◆法人と個人の財産の混同◆
破産手続は法人格毎の手続です。法人と個人とは明確に区別されます。会社、法人の資産と個人との間の混同を避けてください。特に会社、法人から個人への財産移転は慎重にしなければなりません。
この点で、経営者家族の役員報酬、給与も問題になり得ます。事業廃止までの役員報酬、給与は、支払う原資があるのであれば支払って問題はないでしょうが、その他は弁護士と相談してください。
弁護士に依頼する意味(倒産弁護士)
1.破産申立代理を弁護士に依頼する意味
会社、法人の破産の申立てには、代理人弁護士を依頼することが通常です。会社、法人の破産は複雑であり、弁護士の助けがなければ難しいです。◆地図を作りナビゲーションを行う◆
ご相談者は初めは何をどのようにすればいいかわかりません。弁護士に複雑な状況を法的かつシンプルに整理してもらい(地図を作ってもらい)、弁護士の助言(ナビゲーション)に従って、効率的なご準備をしてください。
暗中模索の中で今後のことを悩まれるのは大変な心労です、「何もわからなかった頃が一番辛かった。依頼してよかった。」とおっしゃる方が多いです。
◆債権者対応を弁護士に任せる◆
取引先や金融機関への支払を停止すると、程度の差はあれ混乱が生じます。債権者の対応を弁護士に任せられることは安心です。
◆申立後のサポート◆
破産手続が開始されてからは破産管財人が破産手続を主宰しますが、申立代理人弁護士も破産手続の最後までサポートをします。ご安心ください。
2.倒産弁護士
◆申立代理人の腕が手続の帰趨を決める◆申立代理人弁護士の腕が、破産申立ての準備のご苦労の程度や申立て後の手続のスムーズな進行度合いに直結します。準備に不備があると、申立て後に苦労を強いられかねませんし、行為が問題視されることもあります。
当職が破産管財人に就任した案件でも「準備をもう少しきちんとしていただければ苦労されなかったのに。」と感じることがあります。
◆倒産案件の弁護士業務は職人芸◆
破産手続は、破産法に則っています。当然、破産の準備には、破産法の知識・倒産事件の経験が必要です。かつ、破産手続には、独特のルールや考え方があり、それに携わる弁護士も職人的な能力が必要とされます。場数も必要でしょう。
破産申立てを裏から見る破産管財人の経験も必須です。特に法人破産の破産管財人の経験が豊富でなければ手続の勘所がわかりません。その時々の破産裁判所の傾向・考え方も事件処理の方向に影響しますので、それらもキャッチアップしなければなりません。
破産等倒産手続に精通した弁護士のサポートを得てください。
◆企業会計の知識◆
会社・法人破産の申立ては、資金繰り、事業廃止・受任通知のタイミング、資産・契約関係の整理など様々な段取りを考えないといけませんね。そのため、企業会計に関する諸知識も必要です。
まずは決算申告書類等の会計書類を拝見して事案の見立てを行い、個々の問題を紐解いていきます。
◆倒産弁護士、破産弁護士◆
倒産法制に精通し、申立て代理人経験も破産管財人等の経験も豊富で、破産等倒産事件を業務の柱の1つにしている弁護士を「倒産弁護士」、「破産弁護士」と呼ぶことがあります。「離婚弁護士」なんてドラマもありましたね。
会社、法人の破産の申立てを依頼するのであれば、当然、そのような弁護士に依頼した方がいいでしょう。
弁護士の質を確かめるには、相談する弁護士に細かいことでもたくさん具体的な質問を投げかけてください。あなたの望む弁護士であれば、抽象的な回答にとどまらず、具体的なアドバイスをしてくれるでしょう。
なお、当職も、申立て代理は勿論、破産管財人経験も豊富で、破産等の倒産案件を業務の柱の1つとしています。裁判所との破産等に関する協議会のメンバーにもなっております。また、銀行出身であり、企業会計の諸知識も豊富です。安心してご相談いただけるものと自負しております。
まとめ
1.会社、法人の自己破産の決断にあたって
自己破産の説明や自己破産を選択すべきケースなどの説明をさせていただきました。社会的価値のある事業はできるだけ継続するべきですので、リスケやM&Aにより事業継続を図ることが優先されるでしょう。
しかし、会社、法人の自己破産は最後の手段ではありません。事業継続の可能性を見極め、自己破産の決断を早期に行うことも大事な経営判断です。
弁護士に相談するタイミングの説明もさせていただきました。できるだけ早く弁護士に相談し、事業継続の可能性を見極め、事業継続の可能性に沿った適切な選択をしてください。
費用面も説明させていただいたとおり、弁護士と相談すればいいことです。
経営者に必要なのは、適切な助言を得ることと決断することです。当事務所にぜひご相談ください。
2.会社、法人の自己破産の準備にあたって
自己破産の流れ、取引先や従業員との関係あるいは破産準備の注意点等をお話しいたしました。会社、法人の自己破産は、様々な課題を抱えており、それを整理して1つ1つ紐解いていかなければいけません。
海図と羅針盤なくして進んではいけません。準備の内容や程度はケースバイケースで異なり、やってはいけないことも存在します。倒産弁護士とともに、事業廃止のタイミングを見極め、やるべきことを整理した上で、ナビゲーションに沿った準備を進めてください。効率的な、かつ適切な準備が後の破産手続のスムーズな進行に直結します。
当事務所にご相談いただければ幸いです。
この記事を書いた人
 弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)
弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27
アーバンビュー上八丁堀602
TEL:082-223-2900
https://www.nakata-law.com/
https://www.nakata-law.com/smart/
◆経歴
1996年4月 あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月 東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月 広島大学大学院法務研究科
2008年12月 弁護士登録
2017年~各前期 広島大学大学院客員准教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)
(なかた法律事務所) 2020年5月 7日 14:43
中小企業のM&A価格の考え方 [企業法務]
今回の企業法務コラムでは、中小企業のM&Aの代金額の決定方法のお話しです。
当職は、M&Aに関わることが割合多く、最近は常に案件に携わっている状態が続いています。
すべて中小企業のM&Aです。
M&Aといっても、その形態はほぼ株式譲渡か事業譲渡です。
合併や会社分割を絡めたM&Aのニーズやメリットは中小企業にはあまりありませんので。
関わり方はケースバイケースです。
交渉から関わるケース、買い手売り手双方のコーディネーターとしてかかわるケース、契約関係や法定手続だけサポートするケースなど、依頼者のニーズに合わせた関わり合いをします。
いただく費用も関わり合いに応じて千差万別です。
しっかり財務デューデリジェンスをする案件では、税理士と弁護士がセットでお手伝いします。
今回は買収価格の決定方法の話です。
勿論、買収価格の決め方には決まりはありません。
当事者が自由に決められます。
不当に安いあるいは不当に高い価格での売買には税務上のリスクがあるだけです。
もっとも、決めるのには目安がないといけませんね。
株式譲渡であれば、株式の価格です。
事業譲渡では対象事業(物も含めて)の価格です。
税務上の株式評価(相続税評価)は使いません。税金のための評価ですからね。
評価方法はいくらかありますが、経験上、中小企業の株式譲渡は、
時価純資産価格+営業権価格
あるいは
そのどちらか一方、
を目安に決めることが多いです。
時価純資産は、決算書あるいは試算表の純資産をベースに、含み益をプラスし、含み損をマイナスして算出された、所謂、清算価値・純資産価格ですね。
要するに、株式が表章する会社のモノ・カネの価格です。
この純資産価格ベースでの価格決定も多いです。
利益があまり出ていない会社はこれだけで十分だからです。
営業権価格は、会社が将来生む利益あるいはキャッシュフローを価格に反映させるものです。
営業権価格の計算は、
利益(キャッシュフロー)×1~5年
で行いますが、それぞれどの数字を持ってくるかが重要になります。
それにより数字はかなり変わりますから。
利益には、基本的に営業利益を持ってくるでしょうか。
減価償却費をプラス、時にはオーナー役員報酬の全部または一部をプラスするなどして、キャッシュフロー的な数字を持ってくることも多いです。
経常利益を使うこともあるでしょう。こちらの方が収益力が正しく反映されていることがあります。
ケースバイケースですね。
期間は、3年がスタンダードでしょうか。
業種や業態により、短ければ1年、長ければ5年でしょうか。
価格の目安が決まったとして、実際の契約価格を決めるには別の考慮をします。
売主が個人の株式譲渡のほとんどでは、前オーナーは会社を退きます。
株式譲渡による譲渡所得税よりも退職所得の方が一般的に有利です。
そこで、売り手には株式譲渡代金と退職金とを分けて受け取ってもらうことが多いです。
買い手にも損はありませんし。
総額を決めて、役員退職金をいくら受け取れるか検討し、残額を代金額にするというイメージです。
退職金支給により株式の価値は下がりますから当然といえば当然です。
次は事業譲渡の価格ですが、基本点には株式譲渡の価格の考え方に準じます。
全ての資産を含めた全事業を譲渡する場合には、株式譲渡と変わりませんね。
ただ、看板名を変えることのリスク、従業員を引き継げるかのリスク、取引口座を引き継げるかのリスクなど、価格マイナス要因はあるでしょう。
全ての事情譲渡であれば株式譲渡でもいいのですが、売り手の債務・リスクを遮断したいときには、債務を引き継がない形の事業譲渡にすることがありますね。
逆に、免許や取引先の関係で株式譲渡の方法しかとれないケースもあります。
一部の事業譲渡、あるいは資産を引き継がない事業譲渡では、引き継ぐ資産の時価に引き継ぐ事業の営業権価格を加えた金額が一応の価額の目安になります。
最初にお話ししたように、M&Aの価格は自由に決められます。
実際に、売り手・買い手のパワーバランスによって価格は大きく左右されます。
また、業種によっても様相が変わります。
いろんな業種のM&Aに携わると、様々なことに気付きます。
事業承継の一環として、後継者のいない会社のM&Aが増えているようです。
事業承継は後継者に引き継ぐか売却するかの2者択一ですからね。
逆に言えば、現在では、会社を買うチャンス、顧客・市場を獲得するチャンスも増えているということです。
事業承継の一環として、あるいは経営戦略の1つとしてM&Aをお考えになることもいいと思います。
顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2019年10月 4日 17:36